| 対談集「対話の文明」に学ぶ ① 23年01月19日 |
テーマ 宗教と対話 創価大学で語り合う池田先生とドゥ博士(2005年4月)。先生は「対話の文明――まさに現代世界を変革する急所を、博士は見つめておられる」とたたえた。博士は「SGIからは、さまざまな知的な刺激を受けています。私の精神を啓発する源泉です」と 池田大作先生の著作から、現代に求められる視点を学ぶ「人間主義の哲学の視座」。感染症のパンデミックによる混乱やウクライナ危機などに象徴される、世界の分断化にどのように向き合えばよいのか。今回からは「宗教と対話」をテーマに掲げ、ハーバード大学のドゥ・ウェイミン博士との対談集『対話の文明』の「第2章 文明の差異を超えて」をひもとく。 【池田先生】 対話とは“他者を変える”よりも まず“自分を変える”壮大な挑戦 【ドゥ博士】 宗教者は“信仰共同体の言語”と “地球市民の言語”を語る必要が 差異を超えて 第2章の冒頭、「21世紀を開く対話の要件」と題された節には、次のエピソードが紹介されている。 夏の浜辺でくつろぐ、互いに見知らぬ2組の家族がいた。 1組の家族の子どもが海に入り、溺れてしまう。それを見つけた、別の家族の父親が海に飛び込み、子どもを助ける。しかし、子どもを連れ戻す際、今度は自分が溺れてしまう。 助けられた子どもの家族が信仰するのはユダヤ教で、助けた父親はイスラム教を信仰していた。そうした垣根など一切越えて、目の前の子どもの命を、自分の命を懸けて救ったのだ――。 これは国連が定めた2001年の「文明間の対話年」に当たって設置された賢人会議の報告書「差異を超えて」に収められているものだ。同会議は、ドイツのヴァイツゼッカー元大統領やノーベル経済学賞のアマルティア・セン教授ら18人の識者によって構成され、ドゥ博士もそのうちの1人として報告書をとりまとめた。 あらゆる文明において、「差異を超えて」地球的課題に取り組むことを促すには、その基盤となる宗教にもまた、その宗派性を超えた行動が求められる。池田先生は「いかなる高等宗教も、究極的には『人間の幸福』『社会の平和』を志向している。その共通の大地に立てば、希望の未来の建設へ共に協力し合っていけるはずです」と展望する。 「開かれた」姿勢 そうした高等宗教の取り組みにあって、宗教指導者の役割は重要だ。その集団に直接関わる問題のみに取り組む「閉ざされた」姿勢にとどまることなく、地球的問題を視野に入れて行動する「開かれた」姿勢であることが求められよう。 〈ドゥ〉 私たちがとくに関心をもっていることは、宗教指導者たちが地球市民の一員として、その精神的源泉を人類全体の幸福のために活用し、人類が置かれている状況に関する私たちの認識と理解を助けてくれるよう、働きかけることです。 〈池田〉 まさに急所を突いた洞察です。もはや、一宗一派に閉ざされた宗教であっては、時代の遺物といわざるをえません。なかんずく、地球的問題群の解決のためには、あらゆる宗教が英知を結集し民衆の幅広い連帯を築いていくことが要請されます。 仏法では“差異へのこだわり”を乗り越えて、対話によって、ともに社会の平和と幸福を目指していくべきことが説かれております。 私どもが信奉する日蓮大聖人の「立正安国論」は、思想や信条が異なる二人の人物が対話を交わす形式で、論が進められています。時に議論を戦わせながら、ともに社会を憂えるという共通の土台に立って、粘り強く真剣に対話を続けていく。そして、悲劇を生み出す原因は何か、悲劇を止める術はあるのか、人間はそのために何をすべきなのか、といった問題意識を共有し語り合うなかで、その方途を見出し、社会のために行動することを確認していくのです。そこでは「対話の力」が生き生きと示されているのです。 ドゥ博士は1989年7月から14カ月間、ハワイ・東西センターの文化・コミュニケーション研究所の所長を務め、世界における「平和の文化」構築への出発点として、「文明間の対話」を推進し、「宗教間の対話」を探求した。その際、あらゆる人間の宗教性を包括する「世界精神性」という土台に立ったことを語った。 〈池田〉 博士のお話を伺いながら、私の師である戸田第二代会長が語っていたことを思い起こしました。 「釈尊やキリストやマホメットらが一堂に会したならば、大きい慈愛の心で語り合い、譲り合い、尊重し合っていくであろう。そして根本的目的である人類の恒久の幸福に向かって、戦争・暴力・紛争を断じて食い止めようと、ともに手を携えて立ち上がっていくことだろう」と。 師は、宗派性を超えた大きな志向性をもっていました。それは、いかなる宗教も人間の幸福に奉仕するものであらねばならないとの信念から出発したものでした。 〈ドゥ〉 「宗教間の対話」のあり方を示す、示唆に富んだお話に心から共鳴します。 現代の宗教者は、一方で“それぞれの信仰共同体の言語”を語るとともに、他方で“地球市民としての言語”を語っていく必要があると思います。この二種類の言語に通じることが、“文化的独自性の要求”および“人類共通の幸福”の両方に応えていくことになるのです。 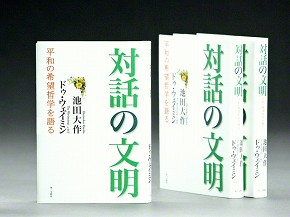 2007年に発刊された対談集『対話の文明』 分断を克服する道 この世から「悲惨」の二字をなくしたい――この恩師の願いを胸に、世界の知性との1600回を超える池田先生の文明間対話、宗教間対話は、まさに差異を超え、人間と人間を結び、分断や対立を協調と連帯へと導く“地球市民の語らい”であるといえよう。 〈池田〉 ナチスと対峙し、亡命先のアメリカで活躍した、思想家のハンナ・アレントは、「ただ世界が人間的となるのはそれが語りあいの対象となった場合に限ります」(『暗い時代の人々』阿部斉訳、河出書房新社)と述べています。 真の「対話」は、人々を結びつけ、相互の信頼をつくり出していくためのかけがえのない磁場となる。対話による善なる力の内発的な薫発こそが、互いの人間性を回復し蘇生させるといえましょう。 〈ドゥ〉 まさに、そのとおりだと思います。対話方式というのは、単に同一性や均一性を求めることではありません。それは「人間になる」ための豊かで効果的な方法なのです。私たちは、異なった生活様式との出合いによって、「聞く」技術や思いやりの倫理観、自己発見の感覚を磨いていくのです。 〈池田〉 おっしゃるとおり、対話の海のなかでこそ、人間は「人間になる」。対話とは、“他者を変える”というよりも、まず“自分を変える”壮大な挑戦といえるでしょう。 政治家や宗教者である前に、「一人の人間」であり、そこに立ち返る。そのためには「対話が不可欠」という点で一致した両者。その「一人の人間」が持つ偉大な力に期待を寄せた。 〈ドゥ〉 私は、池田会長が指摘されてきた「人間主義と共生の『希望の新世紀』を創り出す力は私たち自身のなかにある」という哲学に深く賛同しています。 今や、私たちは、進歩や個人主義にとりつかれた西洋の啓蒙主義(※注)が主流をなしてきた、現代社会の方向性を変えなければなりません。そのために不可欠なのが対話です。相手を説得するというよりも、みずからの視野を広げるために対話を重ねていくことが、分断や対立を克服する道であると、私は信じています。 ◇ 〈ドゥ〉 真の対話は、相互の信頼と理解に基づいて行われなければなりません。そして、真の「文明間の対話」とは、自分のなかに相手の文明を共存させることによって、みずからの文明の地平を開いていくものでなければなりません。こうした真の「文明間の対話」こそが、地球共同体のための「対話の文明」を創出するうえでの有望な手段だと考えるのです。 これに対し、池田先生は、対話が日常のあらゆる場面でなされることを念頭に、この節を次の言葉で結んだ。 〈池田〉 政治、経済をはじめ、あらゆる分野において、正しき対話の精神が最大に重んじられていく。そして、互いに敬い、学び合いながら、自他ともの幸福と繁栄を目指していく。そうした「対話の文明」を築いていくことが、今こそ求められています。 【語句解説】 〈注〉啓蒙主義 近代の自然科学確立とともに、中世ヨーロッパのキリスト教神学を根本とした学問体系から脱し、合理性や科学によって真実を究明しようとする考え。 【プロフィル】 ドゥ・ウェイミン ハーバード大学名誉教授。1940年、中国・雲南省生まれ。ハーバード大学で博士号を取得後、カリフォルニア大学バークレー校の歴史学教授、ハワイ・東西センター文化・コミュニケーション研究所所長、ハーバード・イエンチン研究所所長などを歴任。中国史・思想の大家であり、儒教研究の第一人者。 |