| 太平洋の旭日に学ぶ㊤ 21年06月24日 |
| テーマ:安心と安全 池田大作先生の著作から、現代に求められる視点を学ぶ「人間主義の哲学の視座」。今回からは「安心と安全」をテーマに掲げる。ここでは、パトリシオ・エイルウィン元チリ共和国大統領との対談集『太平洋の旭日』をひもとく。  チリを初めて訪れた池田先生とエイルウィン大統領(当時)が、2度目の出会いを果たす。会談では、「文化交流」の展望を中心に、「民主チリへの期待」「環境保護と経済成長」などが語り合われた(1993年2月、チリの首都サンティアゴの大統領府で) 【池田先生】 社会(自らの足場)への「責任感」を放棄せず 時代を開く主人公の自覚に立つ。 【エイルウィン元大統領】 国家の利益の追求が 人間の尊厳を犠牲にしてはならない。 一人一人の安心と安全が、大きく揺らぐコロナ禍の時代。国連開発計画(UNDP)は本年5月、この新たな時代の「人間の安全保障」の在り方を再考するためのハイレベル諮問パネルを設置した。 「人間の安全保障」は、1994年にUNDPによって提唱された概念である。国家がその国境や国民を守るという「国家の安全保障」の枠を超え、人間一人一人の基本的人権を尊重し、人々が自ら主体者となって安心と安全を実現する社会を目指す(長有紀枝著『入門 人間の安全保障』中公新書を参照)。 池田先生は本年の「SGIの日」記念提言で、パンデミック(世界的大流行)への対応において、「国の垣根を越えて人々が直面する脅威を共に取り除こうとする『人間の安全保障』のアプローチ」が求められていると述べた。 また、「どこかに脅威の火種が残る限り、同じ地球で生きるすべての人々にとって、本当の安心と安全はいつまでも訪れない。どの国も犠牲にしてはならず、世界の民衆の生存の権利が守られるものであってこそ、真の平和の実りをもたらす安全保障となる」と。 コロナ禍という未曽有の危機に向き合う今、国際社会のレベルだけではなく、一人一人の立場で「人間の安全保障」の価値を思索することの意義は大きい。 民主化の実現へ 権力者は不安と恐怖で人々を分断し、指導者は安心と安全を確保して民衆を一つに結ぶ。歴史は、その戦いが繰り返されてきた。 南米・チリ共和国で軍事政権下の不毛な対立に終止符を打ち、平和裏に民主化を実現させたパトリシオ・エイルウィン氏も、そうした挑戦に身を投じた人物である。 氏と池田先生は、日本とチリで3度会談し、対談集『太平洋の旭日』を編んでいる。 15年以上続いた軍事政権を終わらせる契機となったのは、1988年の国民投票である。 投票は、もともと軍政側が権力維持を狙い、独裁的な大統領の留任を国民投票によって正当化しようと計画していたものだった。力によって、勝利を強要できると思い込んでいたのである。 これを逆手にとり、投票によって軍事政権に「ノー」を突き付けようと呼び掛けたのが、エイルウィン氏だった。“賭け”ともいえる提案だったが、氏には確信があった。“国民の過半数が自由を回復したいと熱望している”。結果は、反軍政側の勝利であった。 氏は、90年に同国大統領に就任。その際、敵対していた前大統領の表敬訪問を受け入れたことは、「平和的な政権移行」を予感させるものとして国民から好感をもって受け止められた。 しかし、氏は「新時代を開いた指導者」という栄誉を望まず、ただ「和解の大統領」として人々の記憶の片隅に残ることを願った。政治家として類いまれな手腕を発揮した氏が貫いたのは、どこまでも民衆の心に寄り添うことであった。 エイルウィン 私が望んだことは、――あらゆる同胞たちにとって、一家の良き父のような存在になり、誠心誠意の熱意と献身で、与えられた権限を駆使し、国民の健康と幸福を築きあげたい。とりわけ緊急にその必要に迫られている極貧層の子供たちを優先的に配慮したい――ということでした。 池田 そのような姿勢が、民衆の広範な支持を得られたのでしょう。これは、万般の道理です。 軍事独裁政権のあと、和解を図りながら、国民主役の政策を実行する。荒海にあえてこぎ出すような困難な作業だったがゆえに、信望のあるリーダーと、公平無私なリーダーシップが求められたと思います。その意味では、指導者像というのは、時代と人々が決めるのかもしれません。 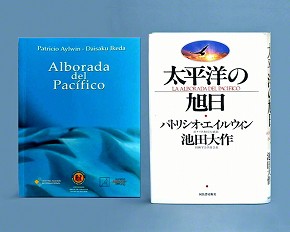 対談集『太平洋の旭日』の日本語版とスペイン語版 本質的な尊厳 “極貧の子供たちを助けたい”と語った氏。人々が安心して生きられる権利を奪う貧困は、「人間の安全保障」に対する脅威にほかならない。さらに氏いわく、貧困とは「平和に対する絶え間のない脅威」である、と。 こうした問題の解決なくして、世界の安全も平和もない。ゆえに先生と氏の語らいは、深く「人権」を論じ合うものとなった。 エイルウィン “国家の偉大さ”とか“階級のない社会の建設”とか“経済繁栄”といった、より緊急性を要すると考えられるものの達成……これらを優先させる必要があるとの口実のもと、人間の尊厳に関する基本的人権の遵守を、犠牲にすることは許されないのです。 池田 科学技術一辺倒になり、豊かな消費世界をひたすら目指すという考えに支配されつつあります。だからこそ、人間の尊厳をしっかりと見据えた、哲学的な基盤をもった“新しいヒューマニズム”が求められます。 エイルウィン 私があえて申し上げたいことは、その人類の一人一人がもつ本質的な尊厳というものは、人類の進歩に深くかかわっており、それがどれほど認められ尊重されているかで、人類の進歩の度合いを測ることができる、ということです。 しかし、現在、私たちはこのことに関して勝利に酔いしれているような状況にないことは明白です。世界には、まだ人権が認められていなかったり、蹂躙されているところがたくさんあり、いずれの国民も人権の後退という危険性と無縁ではないのです。 新たな人権の理念 貧困問題を解決していく上で求められる要件として、先生は、「運命を共有する“地球社会の隣人”としての自覚と責任」を挙げ、貧困撲滅の取り組みの成否は、“人類共闘”の枠組みを確立できるかどうかにかかっている、と語る。 さらに、国際社会の一致した取り組みを進める上で、物的・資金的な援助という“応急処置”だけではなく、長期的な視野に立ち、一人一人の「潜在的な力」を引き出すことのできる環境づくりこそが肝要である、と。 課題克服の鍵を、外的条件の変化とともに、自立やエンパワーメントといった内面の変革に見いだす先生の視点は、「人間の安全保障」の骨格をなす理念でもある。 池田 現代と未来に対応する新たな人権の理念は、人間の暗部も含めて、人間の存在を根底から解明した哲学に裏付けられ、支えられることが要請されます。人間の内奥に潜む「悪」を見つめ、その悪を克服していく方法が示されなければなりません。 エイルウィン 私たちは自分たちの主義主張を宣言として表明したり、自分たちが従うべき規範を作成しますが、往々にして反対のことを行ったり、守らなかったりという過ちを犯します。それがあなたのおっしゃる“人間の内奥に潜む悪”なのです。 私は、悪に対して弱い人間を救済するためには、精神的な支えを確立するしかない、とするあなたの所信に同意します。 池田 仏教の英知は、結論として、人間に限らず、すべての存在に他者への慈愛に貫かれた広大な生命(仏)が内在している、と洞察しています。あらゆる人間生命に仏が内在しているというこの仏教の英知こそ「人間の尊厳」を裏付ける新たな力になり、人間内部に潜む悪を克服していけると私は確信しています。 エイルウィン “仏性”あるいは“ブッダの本質”というものは、私たちキリスト教徒が“聖性(高潔清浄な心)”と呼んでいるものと同じです。各々一人一人が悪を遠ざける徳を有し、完璧を目指して努力することです。 池田 世界は、「『民主主義』には、人間に対する尊敬が必要であり、それを忘れると民主主義への人々の関心が薄れる。そこには全体主義的な社会へと後退する危険がある」とのあなたの主張に真剣に耳を傾ける必要があるのではないでしょうか。 一人一人の人間が自らの足場である社会への責任感を放棄せず、時代を切り開く主人公であるとの使命感を充溢させながら、よりよき世界を目指し連帯していく――私は、そうした人間精神の自律性を回復させていくことが、このアポリア(難問)から抜け出す大前提となると考えるのです。 〈プロフィル〉パトリシオ・エイルウィン・アソカル チリ共和国元大統領。1918年生まれ。51年、33歳でキリスト教民主党の総裁に選ばれ、上院議員、上院議長などを歴任。チリ民主化運動をリードし、89年12月、大統領選挙に勝利。軍事政権にピリオドを打った。大統領在職中(90年3月~94年3月)、貧困の撲滅などに尽力した。2016年4月死去。 |