| 『20世紀の精神の教訓』に学ぶ③ 21年03月13日 |
 池田先生ご夫妻がゴルバチョフ元大統領一家と和やかに。右端から令孫のアナスタシアさん、令嬢のイリーナさん。会見の中で、先生は「いくら『外なる力』が大きくても、『内なる力』を強めなければ、人間がつぶされてしまいます」と、内面への探求の重要性を語った(2003年3月、聖教新聞本社〈当時〉で) 【池田先生】 内なる革命から社会の変革へ 「他者性の尊重」をその柱に 【ゴルバチョフ元大統領】 多様性それ自体が偉大な価値 21世紀の持続的発展の要件 発想の転換 過去に乗り越えたことがないような“人類的危機”に、どんな手段や経験を頼りに立ち向かうのか――。 この問いに、著名な生物地理学者であるジャレド・ダイアモンド氏は答えた。「世界の国々が一致団結して危機に向き合い、乗り越えるには、世界の人びとが共通のアイデンティティを持つことが必要です。そうしたアイデンティティが、行動の方向性に忠誠を尽くすことを可能にするからです」(クーリエ・ジャポン編『新しい世界』講談社現代新書) 近著『危機と人類』で、国家的危機に直面した各国の変革を描いた氏の、気候変動を巡る考察である。 気候変動、そして核兵器という、人類の存続を左右する脅威に加えて今、感染症のパンデミック(世界的大流行)が地球規模で続く。立ち向かう私たちに求められるのも、この時代を「自分は」どう生き、世界に対して何ができるのかというアイデンティティー(自分であることの根拠)の確立だ。 物事を“自分事”と捉え、自身を磨き上げることで「変革の波」を広げていく――これが創価の人間革命運動であり、池田先生とゴルバチョフ氏が語り合ったテーマでもあった。 池田 21世紀を展望するうえで、不可欠なポイントとなるであろう点を一つ、問題提起したいと思います。それは、思考の回路を「外」から「内」へ、だけでなく、「内」から「外」へ、つまり「環境革命」から「人間革命」だけでなく、「人間革命」から「環境革命」へと方向転換していく、ということです。 ゴルバチョフ わが国が迎えた崩壊と騒乱の時代は、太古よりの理性と本能の葛藤に、たしかに新しい局面を登場させました。今ロシアが学んでいる歴史の教訓は、全人類の関心を呼ぶものだと思います。 池田 20世紀は、文明の進歩とは裏腹に、史上かつてないおびただしい人命の犠牲がもたらされました。 「外」なる条件、すなわち法や制度、経済などの面から、民族的・階級的矛盾を解消することが、おしなべて人間社会の幸・不幸を決定づける根本要因とされてきたわけです。 私は、今こそ人間の内面へ視線を移し、「内」なる課題の解決を第一義にしつつ、「内」から「外」へと、発想の転換をはかっていくことが必要であると思います。 桜梅桃李の個性 自己の内面の転換を促す「新しい精神性」は、どのようにして芽生えていくのか――。先生は大切な点として、他者の存在に対して謙虚であろうとする「他者性の尊重」と、絶えざる努力による、その「習慣化」を挙げる。 また、仏法に説かれる「桜梅桃李」を通して、世の中の花が桜だけであればそれは個性とはいえず、梅や桃といった“他者”の存在があってこそ、桜の個性は際立ってくると強調。このことは、人間であっても同じであると訴える。 池田 自己の内面に「他者」を見失い、「他者」との結びつきを断たれ、一見活動的なようでも精神世界が外から閉ざされてしまっている、いわば“自閉的状況”は、20世紀文明の産み落とした最大の病理とはいえないでしょうか。 ゴルバチョフ 世界・人間・社会の多様性を認めることは当然として、その多様性それ自体が、じつは偉大な価値であることを認識すべきです。一元化を標榜するボルシェビズム(※注1)、さまざまな所有形態、階級を認めない考え方。それにまっこうから挑戦するところから、ペレストロイカ(※注2)が始まったことはすでに申し上げました。その道程にあって、私たちは、決定的な一歩を印すことができたと自負しています。 私は、この多様性の尊重こそが、来るべき世紀の重要な原則となり、安定した持続的発展の要件となると確信しています。 「立正」と「安国」 他者性とは「相手の側に立ち」「相手と自分を入れ替えてみる」こと――文豪ゲーテの言葉を引いて、先生は率直に語った。 ここで氏は、そうした“内なる変革”は決して容易ではないと述べる。母国の政治改革に奔走しながらも、国民の心を変えることの困難さを、その身で痛感した経験からである。 ゴルバチョフ ロシア農民の貧しさを代表する一人である私としては、忘れられない事実があります。つまり、飢えで死のうとしている人間が、「良心」や「善の声」に耳をかたむけるのは、きわめてむずかしいということを、私はよく知っているのです。 幸運な、富める人々にとっての「外なるもの」の価値と、赤貧の、人生に打ちのめされた人々にとっての「外なるもの」がもつ意味・価値とは、おのずから違っています。むろん、一人一人の人間の内面に善を見いだし、「内」から「外」への方向性を支え伸ばしていくことに、課題がおかれていることは十分理解したうえで、あえて申し上げているのです。 池田 よくわかります。現実と向き合うことをさけ、たんに理想のみを追い求める生き方は、私どもの最も忌むところです。 大乗仏教の精髄は、こうした現実の苦悩を直視し、原因を究明し、それをどう解決していくかという課題のうえに成り立っているのであり、決してこの世の悪や矛盾から目をそらそうとするのではありません。 確認しておきたいのは、宗教が救済を志向するにあたって、宗教的価値と世俗的価値との関係のあり方、両者のどちらにウエイトをおくかという、人類の宗教史を深くつらぬいているテーマです。 「立正安国」という言葉は、その関係性をまことに簡潔に示しています。すなわち「立正」という宗教的価値と、「安国」という世俗的価値とは、どちらが欠けても不十分であり、その二つが相まってこそ、「立正安国」という仏法者の使命は達成できるのだ、と位置づけているのです。 私が「内」から「外」へ、と訴えているのも、まさにこの「内なる革命」の「外」へ向けてのやむにやまれぬ発現にほかなりません。 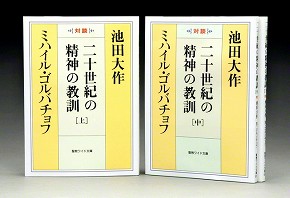 対談集『20世紀の精神の教訓』(聖教ワイド文庫版) 本年1月に発表した「SGIの日」記念提言で、先生は、世界の国々を一隻一隻の船に例え、コロナ危機という“同じ問題の海”を航海しながらも、人類は別々の方向に押し流されてしまう恐れがあると指摘した。そして、この“海図なき航海”の羅針盤となるのが、各国の連帯であると訴える。 他者の苦しみに思いをはせ、身近な場所から行動を起こす――。こうした「他者性の尊重」に貫かれた「内なる革命」の連帯こそが、危機を克服し、より良い世界を創る希望となる。 【語句解説】注1 ボルシェビズム ソ連建国を指導した革命家・レーニンに代表されるボルシェビキ(ロシア社会民主労働党の多数派)の思想的・政治的立場のこと。転じて、過激主義の意としても使われる。 注2 ペレストロイカ 1985年にソ連共産党書記長に就任したゴルバチョフ氏が掲げた、社会的・経済的改革のスローガン。ロシア語で「改築」「建て直し」の意。グラスノスチ(情報公開)とともに、氏の主要政策の一つ。 |