| 対談集「地球平和への探究」に学ぶ 2020年08月15日 |
| 「利他の精神」 新型コロナウイルスの感染拡大によって、現代社会が抱える課題がより鮮明となり、私たち一人一人の生き方が改めて問われている。新企画「人間主義の哲学の視座」では、この危機の時代に求められる哲理を、池田先生の著作から学んでいきたい。第1回は「利他」をテーマに、パグウォッシュ会議の会長を務めたジョセフ・ロートブラット博士との対談集『地球平和への探究』をひもとく。 ■池田先生自身のエゴイズムの殻を打ち破り、他者に同苦する「開かれた人格」を ■ロートブラット博士他人を思う行動が自分を利する。それが文明の基本的教訓の一つ  池田先生とロートブラット博士の初めての会談(1989年10月11日、大阪・関西国際友好会館<当時>で)。博士は、「『世界平和』という同じ目的に向かって行動し、戦っておられる先生とお会いでき、きょうは“勇気百倍”の思いです」と、笑顔で語った 人間であることの条件 フランスの経済学者ジャック・アタリ氏は、著書『危機とサバイバル』(2009年刊)でいち早くパンデミック(感染症の大流行)の脅威に言及したことで知られる。 新型コロナウイルスによるパンデミックの後、氏は自身のホームページに、「ポジティブに考えて生きよう!」と題する一文を掲載。その中で、感染症拡大の危機にあって、①最前線で奮闘する方々への感謝②苦しむ人々への共感③解決策を見いだす人々への称賛④他者のために献身する利他の精神――という4点を、私たちは学ばなければならないと指摘した。 日本のメディアにも登場した氏は、「利他主義という理想への転換こそが人類のサバイバルの鍵」という点を強調。「利他」に対する関心が高まった。 実際には、感染症という未聞の脅威を前に、感染者への差別や人権侵害なども起こっている。いずれも、他者への配慮や想像力を欠いた行為だ。 池田先生とロートブラット博士との対談集『地球平和への探究』では、グローバル化の進展に伴い、一人一人の「社会的責任」、互いを思いやる「相互依存」の重要性も増すことが予見されている。 〈対談集から〉 ロートブラット 現代社会において私たちは、(中略)完全に孤立して生きていくことは不可能です。他の人々の助けがあって初めて、私たちの生活は成り立つのです。 池田 人間は、さまざまな人々の助けや働きによって、さらには先人の遺産によって生きている。その事実を、謙虚に見つめることが大事です。 ロートブラット どの人も、他の人の貢献の恩恵を受けているから、生活が潤いのある豊かなものになっているのです。 池田 「恩を知る」ことは、人間であることの一つの条件です。「恩を忘れる」ことは、人間として最も恥ずべきことです。自分が今、こうして生きていられることを当たり前のように考えるのは、傲慢です。 ロートブラット そこで申し上げたいのは、もし私たちが他の人の助けに依存しているのなら、私たちも同様に、今度は他の人々を助ける義務があるということです。 他人を思いやる行動をとったほうがよい。なぜなら、結局はそれが、自分を利するからです。これが文明の基本的な教訓の一つです。この簡単な真実を見ることができなければ、私たちは石器時代のような原始的な洞穴生活に戻らねばならなくなるでしょう。 「他人を思いやる行動」が「自分を利する」ことになり、それが「文明の基本的な教訓の一つ」――博士の指摘は、コロナとの共存が前提となる「新しい日常」を構築する上で、一人一人が根幹に据えるべき視座であろう。 「小我」から「大我」へ ロートブラット博士が対談集の推敲を終えたのは2005年8月上旬。博士の平和行動の原点となった広島・長崎への原爆投下から60年の夏だった。 その8月の31日、博士は“遺稿”の完成を見届けるかのように、96歳で息を引き取る。 核廃絶に生きた博士の生涯は、激動の20世紀そのものであった。 1908年、博士はポーランドのワルシャワに生まれた。第1次世界大戦では、ドイツ軍に家財を全て奪われ、困窮生活を強いられた。さらに第2次世界大戦では、最愛の妻がナチスのホロコーストの犠牲となった。 博士は、ナチスによる原爆製造を危惧し、アメリカの原爆開発計画「マンハッタン計画」に参加。だが、ナチスが原爆を製造していないという確証を得ると、ただ一人、計画を離脱する。 45年8月6日、博士はラジオのニュースで広島への原爆投下を知り、愕然とする。一般市民に核兵器が使用されることはないと信じていたからだ。 核兵器の“恐怖の均衡”による抑止力が当然のように叫ばれる中、博士は核軍拡競争を食い止めるべく、平和のための科学者の連帯「パグウォッシュ会議」の会長として核廃絶に奔走。95年にノーベル平和賞を受賞した後も、平和活動に駆け続けた。 〈対談集から〉 ロートブラット 「善」のために力を合わせるのか、それとも互いに破壊し合うのか。私たちは「いかにして共に生きるか」を学ばなくてはなりません。そうでないと、互いに殺し合う終末を迎えるしかないのですから。 池田 私が希望を見いだすのは、近年、遠く離れた地域で、飢餓や紛争などに苦しむ人々に対して、世界の人々が強い「関心」を共有し始めている点です。「同苦」ともいってよい感情が生まれています。こうした傾向がさらに強まっていけば、時代は徐々に変わっていくでしょう。いな、断じて変えていかねばなりません。 対談の中で、博士が繰り返し言及したのが「忠誠心」という言葉だ。博士は忠誠心を“同心円”に例えた。 その同心円は、家族、近隣、国家へと大きくなる。そして最も大きな同心円が、人類全体への忠誠心――そう主張する博士に、先生はこう応じた。 「仏法では、エゴイズムにとらわれた小さな自身のことを『小我』と呼びます。そして、その『小我』を超克し、一切衆生の苦を我が苦となしゆく『開かれた人格』のことを『大我』と呼ぶのです」 「この『小我』から『大我』へと境涯を拡大し、やがては社会の変革をも成し遂げゆく運動を、私たちは『人間革命』と名づけているのです」 〈編集後記〉 パグウォッシュ会議が発足したのは1957年。この年の9月8日、戸田先生は「原水爆禁止宣言」を発表し、「人間の生存の権利」を脅かす核兵器は「絶対悪」と断じた。その根底にある「人間生命の変革を」との信念は、ロートブラット博士が署名し、「人間性」に鋭く迫った「ラッセル=アインシュタイン宣言」の理念と響き合う。 両宣言の魂が凝縮した対談集には、核兵器の存在など、人類に関する多くの危機は、人間自らに帰着するがゆえに、必ず乗り越えていけるとの信念が刻まれている。 〈対談者のプロフィル〉 ジョセフ・ロートブラット:物理学者。パグウォッシュ会議名誉会長。1908年11月生まれ。英国で核物理学を研究し、米国の原爆開発計画「マンハッタン計画」に招かれ渡米。ナチス・ドイツが原爆を製造しないことが分かると、同計画から離脱。その後の人生を核兵器廃絶運動にささげた。1955年、「ラッセル=アインシュタイン宣言」に署名した11人の一人。57年、核兵器廃絶を目指す科学者の連帯「パグウォッシュ会議」を創設。95年、同会議と共にノーベル平和賞を受賞した。2005年8月死去。 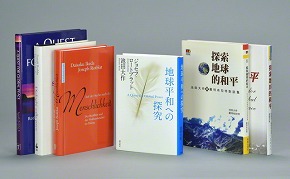 対談集『地球平和への探究』は英語版、イタリア語版、中国語版、ドイツ語版が刊行。電子書籍でも発刊されている |