|

心の財
「豊かな『心の財』を得た幸福境涯というのは、内面的なものですが、それは、表情にも、言動にも、人格にも表れます。
その言動には、感謝と歓喜と確信があふれるものです。そして、思いやりに富み、自分の我を貫くのではなく、皆のために尽くそうという慈愛と気遣いがあります。
さらに、人びとの心を包み込むような、柔和で、朗らかな笑顔があるものです。
また、幾つになっても、向上、前進の息吹があり、生命の躍動感があります。(中略)」
真実の幸福である絶対的幸福境涯を確立できるかどうかは、何によって決まるか。
――経済力や社会的な地位によるのではない。学会における組織の役職のいかんでもない。ひとえに、地道な、信心の積み重ねによって、生命を耕し、人間革命を成し遂げてきたかどうかにかかっている。
(第25巻「共戦」の章、155~156ページ)
皆に光を
皆が広布の主役である。ゆえに、一人ひとりにスポットライトを当てるのだ。友の心を鼓舞する、励ましの対話を重ねていくのだ。(中略)
「日蓮大聖人は、四条金吾や南条時光をはじめ、多くの弟子たちに御手紙を与えられた。その数は、御書に収録されているものだけでも、実に膨大であります。
それは、何を意味するのか。一言すれば、広宣流布に生きる一人ひとりの弟子に対して、“何があろうが、断じて一生成仏の大道を歩み抜いてほしい。そのために、最大の激励をせねばならない”という、御本仏の大慈大悲の発露といえます。
一人でいたのでは、信心の触発や同志の激励がないため、大成長を遂げることも、試練を乗り越えていくことも極めて難しい。私どもが、個人指導を最重要視して、対話による励ましの運動を続けているゆえんも、そこにあるんです」
(第27巻「正義」の章、209~210ページ)
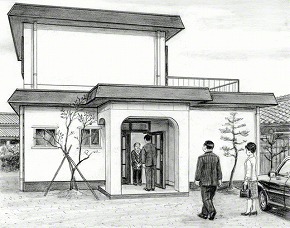
三重の支部婦人部長宅を激励に訪れる伸一(1978年4月)
人間革命
「現代は、エゴの渦巻く社会です。他を思いやる余裕もなければ、冷酷なほど利己主義が深まっています。家庭には不和、社会には複雑な葛藤、争いが絶え間ない。
その根本的な解決の道は、信心による生命の変革、つまり、人間革命しかありません」
生命の内奥から込み上げてくる人間の感情や欲望は、道徳や規律、また制裁の強化など、制度の改革をもってしても、根本的に抑制することはできない。一切の根源をなす生命そのものの変革、心の変革こそが、個人の幸福を実現していくうえでも、世界の平和を築いていくうえでも、最重要のテーマとなる。(中略)
「わが心を磨き、生命の変革を可能にするのが御本尊の力です。仏法を自分の狭い見識の範囲内で推し量ってはならない。そして、御本尊の無限の力を引き出していく具体的な実践が唱題なんです」
(第29巻「清新」の章、298~299ページ)
人材育成
「忘れないでいただきたいことは、会員の皆さんがいて、その成長のために心を砕き、献身することによって、自己の向上があるということです。つまり、幹部にとって会員の皆さんは、すべて、人間革命、一生成仏へと導く善知識になると確信していただきたい」(中略)
「よく、『何人、優れた人を生むかによって、その指導者の価値が決まる』と言われます。仏は、一切衆生の成仏を使命とされ、喜びとされている。
仏子である私たちも、それぞれの立場で、後輩が自分より立派な指導者に育ち、活躍してくれることを祈り、それを望外の喜びとしていきたい。また、そこに、広宣流布のリーダーの生きがいがあります。どうか、後輩と共に動くなかで、信心の基本を、一つ一つ教え伝えていってください。“共戦”こそが人材の育成になります」
(第26巻「奮迅」の章、369~370ページ)

1978年2月、東京・立川文化会館の本部幹部会で指導する伸一
仕事
「腰掛け的な気持ちや、“どうせ自分なんか取るに足らない存在なんだ”という思いがあれば、本当にいい仕事はできません。戸田先生は、よく『ただ月給をもらえばよいというのでは、月給泥棒だ。会社のために、自分はこう貢献したというものがあって、初めて、月給をもらう資格がある』と語っておられた。そして、『“信心は一人前、仕事は三人前”してこそ、本当の学会員だ』と厳しく指導されていた。
大聖人が『御みやづかいを法華経とをぼしめせ』(御書1295ページ)と仰せのように、自分の仕事を信心と思い、仏道修行と思って挑戦していくことです。限界の壁を破り、不可能を可能にするという学会の指導や活動の経験も、仕事に生かされなければ意味がありません」
伸一は、“皆が職場の第一人者に!”との祈りを込め、魂をぶつける思いで語った。仏法は勝負である。ゆえに、社会で勝利の実証を示してこそ、その正義が証明されるのだ。
(第24巻「灯台」の章、295~296ページ)
健康
「健康増進のためには、“健康になろう”“健康であろう”と決め、日々、朗々と唱題し、満々たる生命力を涌現させて、勇んで活動に励むんです。
そして、食事、睡眠、運動などに、留意していくことが、健康のためには必要不可欠です。当然、暴飲暴食や深夜の食事は控えるべきですし、必要な睡眠時間を確保するとともに、熟睡できる工夫も大事です。
また、生活のなかに運動を上手に取り入れて、体を鍛えていくことも必要です」
初代会長・牧口常三郎は、七十歳を過ぎても、国家権力の弾圧で投獄されるまで、元気に、広宣流布のために奔走してきた。彼は、心身の鍛錬を怠らなかったのである。(中略)
「健康は、基本的には、自分で守り、自分で管理するしかありません。最終的には、自己責任です。自分の体のことを、いちばんよくわかるのは、自分であるともいえます」
(第25巻「人材城」の章、324~325ページ)
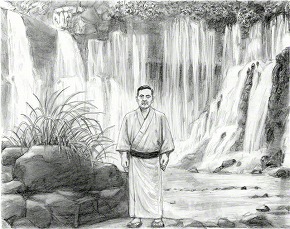
白糸の滝の前に立つ牧口常三郎初代会長
山本伸一と各方面の友
中国
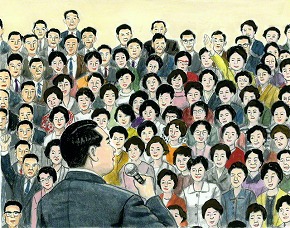
島根県松江市の記念撮影会で励ましを送る(1967年3月5日)
<1967年(昭和42年)3月4日、山本伸一は、中国文化会館(当時)の落成式に臨んだ>
伸一は、全国に先駆けて、中国地方に文化会館が誕生したことが、何よりも嬉しかった。(中略)
彼は、広布の新しき飛翔のために、中国地方を極めて重要視していた。中国は、西日本の大動脈である。中国が大前進を開始すれば、関西にも、四国にも、そして、九州にも、その波動は伝わっていく。まさに、中国こそ、西日本の前進の要であると、伸一は考えていた。
世界で初めて原爆が投下された広島がある中国は、世界の恒久平和を実現する生命の大哲学の、発信基地であらねばならない。
(第11巻「躍進」の章、346~347ページ)
四国
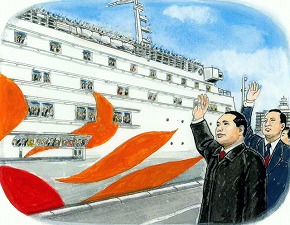
「さんふらわあ7」号の四国の同志に手を振る山本伸一(1980年1月14日)
<1978年(昭和53年)1月20日、山本伸一は香川県の婦人部総会に出席し、四国への期待を語った>
「四国は、方面としては小さいかもしれないが、広宣流布の前進の模範が示せれば、それは、全学会に波動していきます。前進なきところには、仏法の脈動はない。(中略)皆さん方も、“よし、一遍でも、百遍でも、多く題目を唱えていこう”“毎日、一人の個人指導をやり遂げていこう”など、本年は、それぞれが何か一つ、前進の実りを残していただきたい。
その蓄積は、一年後、さらには、それを五年、十年と続けていった時には、想像もできないほどの、生命の財産となり、人間革命の歴史となります」
|