|
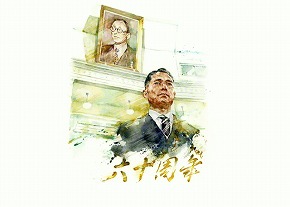
御本尊は生命映す「明鏡」
【御文】
此の御本尊全く余所に求る事なかれ・只我れ等衆生の法華経を持ちて南無妙法蓮華経と唱うる胸中の肉団におはしますなり(御書1244ページ、日女御前御返事)
【通解】
この御本尊を決して別の所に求めてはならない。ただ、私たち衆生が法華経を持って南無妙法蓮華経と唱える、その胸中の肉団にいらっしゃるのである。
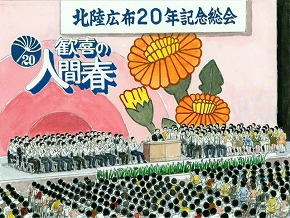
【小説の場面から】
〈1974年(昭和49年)の「立宗宣言の日」にあたる4月28日、山本伸一は、北陸の同志に、御本尊の意義について語る〉
仏は、遠い彼方の世界にいるのではない。また、人間は神の僕ではない。わが生命が本来、尊極無上の仏であり、南無妙法蓮華経の当体なのである。ゆえに、自身の生命こそ、根本尊敬、すなわち本尊となるのである。
そして、その自身の南無妙法蓮華経の生命を映し出し、涌現させるための「明鏡」こそが、大聖人が曼荼羅として顕された御本尊なのである。(中略)
人間の生命を根本尊敬する日蓮仏法こそ、まさに人間尊重の宗教の究極といってよい。そして、ここにこそ、新しきヒューマニズムの源泉があるのだ。
誰もが、平和を叫ぶ。誰もが、生命の尊厳を口にする。
しかし、その尊いはずの生命が、国家の名において、イデオロギーによって、民族・宗教の違いによって、そして、人間の憎悪や嫉妬、侮蔑の心によって、いともたやすく踏みにじられ、犠牲にされてきた。
いかに生命が尊いといっても、「根本尊敬」という考えに至らなければ、生命も手段化されてしまう。(中略)
人間の生命に「仏」が具わり、“本尊”であると説く、この仏法の哲理こそ、生命尊厳の確固不動の基盤であり、平和思想、人間主義の根源といってよい。(「宝塔」の章、300~301ページ)
皆が使命深き地涌の菩薩
【御文】
末法にして妙法蓮華経の五字を弘めん者は男女はきらふべからず、皆地涌の菩薩の出現に非ずんば唱へがたき題目なり(御書1360ページ、諸法実相抄)
【通解】
末法において妙法蓮華経の五字を弘める者は、男女は問わない。皆、地涌の菩薩の出現でなければ、唱えることのできない題目なのである。
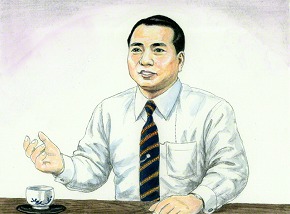
【小説の場面から】
〈1974年(昭和49年)2月、山本伸一は、沖縄の友に広布の使命への自覚について訴える〉
「末法にあって、題目を唱え、広宣流布の戦いを起こせるのは、地涌の菩薩です。(中略)私たちは、どんな宿業に悩んでいようが、本来、地涌の菩薩なんです。
宿業も、末法に出現して広宣流布するために、自ら願って背負ってきたものなんです。でも、誰を見ても、経済苦や病苦など、苦しみばかりが目立ち、地涌の菩薩のようには見えないかもしれない。事実、みんな、日々悩み、悶々としている。
しかし、広宣流布の使命を自覚し、その戦いを起こす時、自らの胸中に、地涌の菩薩の生命が、仏の大生命が厳然と涌現するんです。
不幸や悩みに負けている仏などいません。苦悩は必ず歓喜に変わり、境涯は大きく開かれ、人間革命がなされていく。そして、そこに宿命の転換があるんです」(中略)
法華経の会座において、末法の広宣流布を託されたのが地涌の菩薩である。そして、その上首・上行菩薩の姿を現じられたのが御本仏である日蓮大聖人である。
したがって、私たちは広宣流布の使命に生きる時、地涌の菩薩であるその本来の生命が現れ、大聖人の御生命が、四菩薩の四徳、四大が顕現されるのである。それによって、境涯革命、人間革命、宿命の転換がなされていくのだ。(「宝塔」の章、333~335ページ)
ここにフォーカス 「利他」の一念
「虹の舞」の章で、山本伸一が「利他」の精神を語る場面が描かれています。
彼は、「創価学会の運動の根本をなすもの」は、どこまでも相手のことを思いやる「利他」の一念であり、「この利他の心を人びとの胸中に打ち立てることこそ、平和建設のポイント」と訴えます。
そして、「自分の利益ばかり考える生き方」は、「世の中をかき乱してしまうことになる」と指摘します。
近年、さまざまな分野で、「レジリエンス」という概念が用いられています。「回復力」「抵抗力」のことで、「困難を乗り越える力」を意味します。
心理学でも研究が進んでおり、「レジリエンス」を発揮する要素の一つとして、「信仰に基づく利他の行為」が挙げられています。「利他」の実践は、人生の苦境を勝ち越える要諦でもあるのです。
コロナ禍によって今、人間観や人生観が見つめ直されています。
仏法の哲理は、他者の生きる力を引き出すことによって、自身の小さな殻が破られ、生きる力が増していくことを教えています。“自分さえよければ”という「利己主義」から、自他共の幸福をめざす生き方への転換を促しているのです。
|