|
ブラジルに轟く歓喜のかけ声
〈1974年(昭和49年)3月、ブラジルでは、山本伸一を迎えての文化祭が予定されていた。しかし、学会に対する誤解から、ビザが発給されず、直前で訪問は中止に。伸一は、電話で現地のリーダーを励ます〉
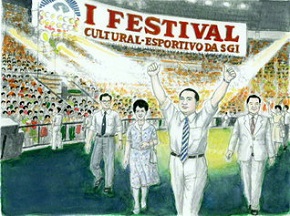
伸一の声であった。(中略)
「辛いだろう。悲しいだろう。悔しいだろう……。しかし、これも、すべて御仏意だ。きっと、何か大きな意味があるはずだよ。勝った時に、成功した時に、未来の敗北と失敗の因をつくることもある。負けた、失敗したという時に、未来の永遠の大勝利の因をつくることもある。ブラジルは、今こそ立ち上がり、これを大発展、大飛躍の因にして、大前進を開始していくことだ。また、そうしていけるのが信心の一念なんだ。
長い目で見れば、苦労したところ、呻吟したところは、必ず強くなる。それが仏法の原理だよ。今回は、だめでも、いつか、必ず、私は激励に行くからね」
(「暁光」の章、81~82ページ)
〈ブラジルの友は悔しさをバネに、祈りに祈り、地域に信頼と友情の連帯を広げた。そして、84年(同59年)2月、当時の大統領の招聘により、ついに伸一の訪問が実現する〉
伸一が、サンパウロ市にある州立総合スポーツセンターのイビラプエラ体育館に姿を見せると、大歓声があがり、大拍手が轟いた。皆、この出会いを、待ちに待っていたのだ。
伸一は、両手を掲げながら、中央の広い円形舞台を一周したあと、万感の思いを込めてマイクを握った。
「十八年ぶりに、尊い仏の使いであられるわが友と、このように晴れがましくお会いできて、本当に嬉しい。(中略)しかし、これまでに、どれほどの労苦と、たくましき前進と、美しい心と心の連携があったことか。
私は、お一人お一人を抱擁し、握手する思いで、感謝を込め、涙をもって、皆さんを賞讃したいのであります」
(中略)大地を揺るがさんばかりの歓声と拍手が起こり、やがて、あの意気盛んな、歓喜と誓いのかけ声がこだました。
「エ・ピケ、エ・ピケ、エ・ピケ、ピケ、ピケ。エ・オラ、エ・オラ、エ・オラ、オラ、オラ……」
皆、目を赤く腫らしながら、声を限りに叫んだ。(「暁光」の章、103~104ページ)
信心は立場や役職ではない
〈1966年(昭和41年)3月、山本伸一は北・南米を訪問。派遣幹部も手分けして中・南米各国を回り、開拓の苦闘を重ねてきた現地の会員を激励する〉

清原たちは、(パラグアイで=編集部注)懸命に御本尊の功力を、信心の大確信を訴えた。確信と揺らぐ心との真剣勝負であった。
三歳ぐらいの男の子を抱えた老婦人が尋ねた。
「この子は孫ですが、生まれつき目が見えないんです。信心を頑張れば、この子の目も、見えるようになりますか」
老婦人の一家は、移住地の人たちに、仏法のすばらしさを訴え、布教に励んできた。ところが、目の不自由な子どもが生まれたことから、「なんで学会員が、そんなことになるんだ」と、批判を浴びせられていたのである。(中略)悲嘆に暮れ果てての質問であった。
皆、黙り込んで、清原の言葉を待った。
彼女は断言した。
「明確なことが一つだけあります。それは、強盛に信心を貫いていくならば、絶対に、幸福になれるということです。このお子さんが、生涯、信心を貫けるように、育ててください。信心をして生まれてきた子どもに、使命のない人はいません。その使命を自覚するならば、必ず最高の人生を送ることができます」
この指導が、世間に引け目を感じ、信心に一抹の不安をいだいていた、この家族の心の闇を、打ち破ったのである。
清原に指導を受けてからというもの、老婦人は、目の不自由な孫が、家の宝だと思えるようになった。そして、家族も、その子どもの幸せを願い、真剣に信心に励み、団結が生まれていったのである。
(中略)木々の生い茂る道を、マイクロバスに揺られながら派遣幹部たちは思った。
“もし、自分たちがこの環境のなかに、ただ一人置かれたならば、本当に信心を貫けていただろうか。皆に指導はしてきたが、学ぶべきは自分たちの方ではないのか……”
信心とは、立場や役職で決まるものではない。広宣流布のために、いかなる戦いを起こし、実際に何を成し遂げてきたかである。
(「開墾」の章、178~182ページ)
学会っ子は負けたらあかん
〈9月18日、阪神甲子園球場で「関西文化祭」が行われた。台風の影響による雨のため、鼓笛隊のジュニア隊の出場は見送られた〉

彼女たちが、出場がなくなったことを知ったのは、白と黄色のユニホームを着込み、今か今かと、開演を待っていた時であった。(中略)
「今回はジュニア隊の出場はなくなりました」
(中略)こう聞かされると、皆、声をあげて泣きだした。
“文化祭で山本先生に見ていただくんや!”と、小さな胸に闘志を燃やし、夏休みを返上して、来る日も来る日も、炎天下で練習を重ねてきたのだ。それなのに文化祭に出ることができなくなったと思うと、悔しくて、悲しくて仕方なかったのである。
ジュニア隊の責任者で女子部の幹部の吉倉稲子にも、少女たちの悔しい気持ちはよくわかった。(中略)しかし、彼女は、心を鬼にして、泣きじゃくる少女たちに、あえて、厳しい口調で言った。
「学会っ子は、何があっても、絶対に泣くもんやない! みんな、山本先生の弟子やろ! 師子の子やろ! 先生は、泣き虫は大嫌いなはずや!」
ジュニア隊の少女たちが泣いていた顔を上げた。彼女は、それから、諄々と諭すように訴えた。
「今日、皆さんの出場を中止にしたんは、皆さんが学会の宝やからです。絶対に、風邪なんかひかせるわけにはいかんからです。(中略)皆さんのことを、一番、心配されているのは、山本先生です。今のみんなの悔しい気持ちも、よくご存じやと思います。残念で仕方ない気持ちはようわかりますが、先生に『私たちは大丈夫です』言うて、ご安心していただいてこそ、鼓笛隊やないでしょうか……」(中略)
吉倉は、涙ぐむ一人の少女の傍らに行き、腰をかがめて、ハンカチで涙を拭いてあげた。そして、肩に手をかけ、体をゆすりながら言った。
「悔しいやろうけど、頑張るんや! これも、文化祭の戦いや! あんたは、絶対に弱虫やない!」
泣いていた少女は、コクリと頷いた。(「常勝」の章、246~248ページ)
難の時こそ師子王の心で進め
〈1967年(昭和42年)4月22日、山本伸一は新潟を訪問。佐渡の地での日蓮大聖人の闘争に思いをめぐらせた〉

日蓮は、佐渡に流されてからも、弟子たちのことが頭から離れなかった。
竜の口の法難以来、弾圧の過酷さ、恐ろしさから、退転したり、法門への確信が揺らぎ始めた弟子たちが、少なくなかったからである。(中略)
弟子のなかには、日蓮に批判の矛先を向ける者もいた。「日蓮御房は師匠ではあられるが、その弘教はあまりにも剛直で妥協がない。我等は柔らかに法を弘めよう」と言うのである。もっともらしい言い方をしてはいるが、その本質は臆病にある。
しかし、その臆病な心と戦おうとはせず、弘教の方法論に問題をすり替えて師匠を批判し、弟子としての戦いの放棄を正当化しようというのだ。堕落し、退転しゆく者が必ず用いる手法である。
佐渡で認めた御書には、弟子の惰弱さを打ち破り、まことの信心を教えんとする、日蓮の厳父のごとき気迫と慈愛が脈打っている。曰く「詮ずるところは天もすて給え諸難にもあえ身命を期とせん」(御書232ページ)と。天も捨てよ、難にいくら遭おうが問題ではない、ただ身命をなげうって広宣流布に邁進するのみであるとの、日蓮の決意を記した、「開目抄」の一節である。
それは、諸天の加護や安穏を願って、一喜一憂していた弟子たちの信仰観を砕き、真実の「信心の眼」と「境涯」を開かせんとする魂の叫びであった。
(中略)さらに、「悪王の正法を破るに邪法の僧等が方人をなして智者を失はん時は師子王の如くなる心をもてる者必ず仏になるべし」(同957ページ)と。法難の時こそ“師子王”となって戦え、そこに成仏があるとの指導である。
(中略)そして、自分を迫害した者たちに対しても、彼らがいなければ「法華経の行者」にはなれなかったと、喜びをもって述べているのである。
これこそ、最大の「マイナス」を最大の「プラス」へと転じ、最高の価値を創造しゆく、大逆転の発想であり、人間の生き方を根本から変えゆく、創造の哲学といえよう。(「躍進」の章、394~397ページ)日刊化を前に、その趣旨などを説明するために、各地で配達員会が開かれたが、どの地域でも、集ったメンバーは、闘志に満ちあふれていた。
新しき広布の幕を開く聖教新聞を、自分たちが支えるのだという、誇りと歓喜を、皆がかみしめていたのであった。
(中略)
山本伸一は、各地の配達員の奮闘を聞くにつけ、深い感謝の思いをいだき、合掌するのであった。
彼は、配達員や取次店の店主らの無事故を、日々、真剣に祈り、念じていた。
また、配達に携わるメンバーが、睡眠時間をしっかりとるために、幹部に、活動の終了時間を早めるように徹底するなど、心を配ってきた。
皆のことが頭から離れずに、深夜、目を覚ますことも少なくなかった。そして、そろそろ取次店のメンバーが仕事に取りかかるころかと思うと、目が冴えて、眠れなくなってしまうのである。
また、全国の天気が、気がかりでならなかった。朝、起きて、雨が降っていたりすると、配達員のことを思い、胸が痛んだ。そんな日は、唱題にも、一段と力がこもった。
山本伸一は、聖教新聞が日刊になって以来、取次店の店主や配達員が、張り合いをもって業務に取り組めるように、さまざまな提案と激励を重ねてきた。その一つが、メンバーが互いに励まし合い、業務の指針となるような、機関紙を発刊してはどうかとの提案であった。
そして、この機関紙は、日刊化一周年にあたる、一九六六年(昭和四十一年)の七月に、月刊でスタートすることになる。
伸一は、メンバーの要請を受け、機関紙の名を「無冠」と命名した。それは、「無冠の王」の意味である。
権力も、王冠も欲することなく、地涌の菩薩の誇りに燃え、言論城の王者として、民衆のために戦い走ろうとする、取次店、配達員のメンバーの心意気を表現したものである。(「言論城」の章、67~71ページ)
誠実の行動が人間共和築く
〈8月、アメリカ・ロサンゼルス南部のワッツ地区で、人種差別に端を発する暴動が発生した。しかし、山本伸一は予定通りアメリカを訪問。15日には、ロサンゼルス郊外のエチワンダで野外文化祭が開催された〉
そこには、人種、民族を超えた、崇高なる人間と人間の、信頼と生命の融合の絆が光っていた。(中略)

騒ぎが起こってからは、白人のメンバーが、ワッツ地区に住む黒人の同志のことを心配し、安全な地域にある、自分の家に泊めたり、練習会場まで、車で送迎する姿も見られた。
(中略)
伸一は、グラウンドを後にし、車に向かう途中、立っていた役員の青年たちに、励ましの声をかけ、次々と握手を交わした。
「ご苦労様! ありがとう!」
青年たちは、頰を紅潮させ、力の限り、伸一の手を握り返した。彼が、役員の青年と握手をしていると、一人のアフリカ系アメリカ人の青年が駆け寄って来て、手を差し出した。その手を握ると、青年は、盛んに、何か語りかけた。(中略)
「山本先生。ワッツで騒ぎが起こっている、こんな危険な時に、アメリカにおいでいただき、本当にありがとうございます。その先生の行動から、私は“勇気”ということを教えていただきました。
また、人びとの平和のために生きる“指導者の心”を教えていただきました。
私は、勇気百倍です。必ず、いつの日か、私たちの力で、人種間の争いなどのない、人間共和のアメリカ社会を築き上げてまいります。ご安心ください」
こう語る青年の目から、幾筋もの涙があふれた。伸一は言った。
「ありがとう! あなたが、広宣流布への決意を定めてくだされば、私がアメリカに来た目的は、すべて果たせたといっても過言ではありません。
一人の人が、あなたが、私と同じ心で立ち上がってくだされば、それでいいんです。大河の流れも一滴の水から始まるように、あなたから、アメリカの平和の大河が始まるからです。わがアメリカを、よろしく頼みます」
その青年は、伸一の手を、両手で、ぎゅっと握り締めた。互いの目と目が光った。
(「幸風」の章、126~132ページ)
“臆病の岬”を越えよ!
〈10月27日、山本伸一はポルトガルのリスボンで、エンリケ航海王子の没後500年を記念して建てられた、新航路発見の記念碑を見学。エンリケは、ポルトガルが大航海時代の覇者となっていった最大の功労者である〉
エンリケによって育まれた船乗りが、アフリカ西海岸を、何度、探索しても、新航路を発見することはなかった。
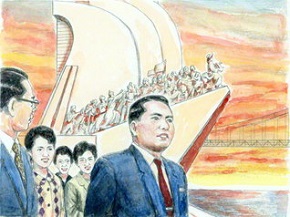
彼らは、カナリア諸島の南二百四十キロメートルにあるボジャドール岬より先へは、決して、進もうとはしなかったからである。
そこから先は、怪物たちが住み、海は煮えたぎり、通過を試みる船は二度と帰ることができない、「暗黒の海」であるとの中世以来の迷信を、誰もが信じていたからだ。
エンリケは叫ぶ。
「岬を越えよ! 勇気をもて! 根拠のない妄想を捨てよ!」
それに応えたのは、エンリケの従士のジル・エアネスであった。(中略)成功を収めるまでは、決して帰るまいと心に決めて出発した。
そして、一四三四年に、ボジャドール岬を越えたとの報告をもって、王子のもとに帰って来たのである。(中略)
カナリア諸島に近い、ボジャドール岬を越えただけであり、新航路の発見にはほど遠かった。しかし、その成功の意義は、限りなく大きく、深かった。
「暗黒の海」として、ひたすら、恐れられていた岬の先が、実は、なんの変わりもない海であったことが明らかになり、人びとの心を覆っていた迷信の雲が、吹き払われたからである。
「暗黒の海」は、人間の心のなかにあったのだ。エアネスは、勇気の舵をもって、自身の“臆病の岬”を越えたのである。(中略)
山本伸一は、しみじみとした口調で語った。
「ポルトガルの歴史は、臆病では、前進も勝利もないことを教えている。
大聖人が『日蓮が弟子等は臆病にては叶うべからず』(御書一二八二ページ)と仰せのように、広宣流布も臆病では絶対にできない。
広布の新航路を開くのは勇気だ。自身の心の“臆病の岬”を越えることだ」
(「新航路」の章、287~290ページ)
今こそ立て! 創価の黄金柱
〈1966年(昭和41年)3月5日、壮年部の結成式が学会本部で行われ、山本伸一が指導した〉
彼(山本伸一=編集部注)の声に、一段と力がこもった。

「壮年部の皆さんは、これからが、人生の総仕上げの時代です。
壮年には力がある。それをすべて、広宣流布のために生かしていくんです。
大聖人は『かりにも法華経のゆへに命をすてよ、つゆを大海にあつらへ・ちりを大地にうづむとをもへ』(御書一五六一ページ)と仰せです。
死は一定です。それならば、その命を、生命の永遠の大法である、法華経のために捨てなさい。つまり、広宣流布のために使っていきなさい――と、大聖人は言われている。
それこそが、露を大海に入れ、塵を大地に埋めるように、自らが、妙法という大宇宙の生命に融合し、永遠の生命を生きることになるからです。
一生は早い。しかも、元気に動き回れる時代は、限られています。壮年になれば、人生は、あっという間に過ぎていきます。
その壮年が、今、立たずして、いつ立ち上がるんですか! 今、戦わずして、いつ戦うんですか! いったい、何十年後に立ち上がるというんですか。そのころには、どうなっているか、わからないではありませんか。
今が黄金の時なんです。限りある命の時間ではないですか。悔いを残すようなことをさせたくないから、私は言うんです!」(中略)
「私もまた、壮年部です。どうか、皆さんは、私とともに、学会精神を根本として雄々しく立ち上がり、創価の城を支えゆく、黄金柱になっていただきたいのであります」(中略)
伸一は、参加者に一礼すると、出口に向かって歩き始めたが、足を止めた。そして、拳を掲げて言った。
「皆さん! 一緒に戦いましょう! 新しい歴史をつくりましょう! 同じ一生ならば、花の法戦に生きようではないですか!」
「ウォー」という歓声をあげながら、皆も拳を突き出した。その目は感涙で潤んでいた。闘魂は火柱となって燃え上がったのだ。(「桂冠」の章、388~391ページ)
|