|
物語の時期 1966年(昭和41年)3月10日~1967年4月22日
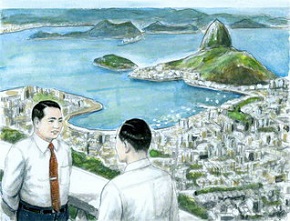
「暁光」の章
1966年(昭和41年)3月10日、山本伸一は5年半ぶりに南米ブラジルを訪問。ブラジルは、会員約8000世帯に達し、サンパウロで文化祭を開催するまでに。しかし、マスコミの誤った情報などから、学会を危険視する空気が強まっていた。彼は、ブラジルの創価学会の目覚ましい発展に、三障四魔が紛然として競い起こってきたのだと同志を励ます。
翌日、伸一は、リオデジャネイロ市内を視察。また、自らブラジルの著名なジャーナリストの取材を受け、学会への偏見を打ち破る連続闘争を開始した。
13日に、サンパウロで開催された南米文化祭などの行事も警察の厳しい監視下で行われた。メンバーは、創価学会の真実を伝え抜き、学会を、先生を、世界一理解し、称賛する国にしてみせると、決意する。

だが、74年(同49年)、ビザが発給されず、伸一の訪問は中止に。しかし、同志は“必ず、先生をお呼びしてみせる!”と、社会の信頼を勝ち得る努力を続ける。そして、84年(同59年)、大統領の招聘によって、伸一の訪問が実現。暗黒の闇を破り、「暁光」を迎えたのだった。
「開墾」の章
伸一たち一行は、ブラジルから、次の訪問地のペルーへ向かう。
3月15日、首都リマに到着した彼は、この日、市内のメトロポリタン劇場で開催される大会に出席する予定であった。だが、ここでもペルー当局の監視の目が光っていた。彼は、熟慮の末、同志を守るために出席を見送る。そして、滞在するホテルの一室で、未来を開くために、同志と懇談。ペルー広布の原野を「開墾」してきた先駆の友をたたえる。

また、彼らに、三点にわたって、人生を勝利する要諦を指導する。第一に、生命力を無限に涌現させる源泉こそが唱題であり、唱題根本の人には行き詰まりがない。第二に、御書をしっかりと拝読し、身で読んでいく教学の重要性をあげる。そして第三には、最後まで諦めずに頑張り通していく信心の持続を訴える。
翌日、伸一は、リマの中心街で、南米解放の英雄サン・マルティンの騎馬像を見つめ、その生涯に思いを馳せる。
また、派遣幹部は手分けして、中・南米各国を訪問。ここにも過酷な環境下で、懸命に学会活動に励む、尊き同志たちがいた。
「常勝」の章
北・南米訪問を終えた伸一は、第一線で活動に励むメンバーとの記念撮影、激励のために、大阪、和歌山、静岡、香川、愛媛など、日本各地を東奔西走する。
彼は、「第七の鐘」が鳴り終わる1979年(昭和54年)を目指し、大前進の指揮を執り続ける。過密スケジュールの中でも、常に未来のことを考え、御書の英語訳の推進など、世界広布の布石を打ち続けていく。

9月18日、伸一は、阪神甲子園球場で行われる「関西文化祭」に出席するため、大阪へと向かう。
当日は、断続的に雨が降り続き、開催が危ぶまれたが、関西の同志は、不屈の関西魂で決行。苦難の雨を、栄光の雨に変え、関西の新たな「常勝」の金字塔を打ち立てた祭典となった。
この頃、伸一は、深刻化したベトナム戦争に胸を痛め続けていた。この凄惨な戦争を、一日でも、一瞬でも早く、やめさせなければならないと、11月の青年部総会で、和平提言を行う。また、73年(同48年)1月1日付で、米大統領に、停戦を訴える書簡を送り、平和のための努力を続けるのであった。
「躍進」の章
山本伸一の会長就任7周年となる1967年(昭和42年)、「躍進の年」を迎える。学会は、前年末に会員600万世帯を達成。伸一は、この一年を、広宣流布の黄金の飛躍台にしなければならないと、強く心に決めていた。
1月9日に関西を訪問したのをはじめ、北海道、九州、中国など2週間ほどの間に国内をほぼ一巡。瞬時の休みもない激闘を続ける。
1月、公明党は初の衆院選で25人が当選を果たし、衆議院第4党となり、大勝利で飾る。
3月4日、伸一は、学会として初の文化会館のオープンとなる中国文化会館の落成式に臨む。彼は、広宣流布とは、人間文化の創造であると考えていた。そして、世界で初めて原爆が投下された広島がある中国方面は、世界の恒久平和を実現する生命の大哲学の、発信基地であらねばならないと確信していた。
4月22日には、新潟を訪問する。そこで9年前の佐渡訪問を回想。その折、彼は、日蓮大聖人の御生涯を偲び、自身もまた、大難に負けず、広布に生き抜こうと誓ったことを思い起こし、決意を新たにする。
雨の関西文化祭

〈1966年9月18日、阪神甲子園球場で開催された関西文化祭。雨による悪条件の中での見事な演技に、観賞した来賓は、称賛を惜しまなかった〉
後に日本写真家協会会長となる写真家の三木淳は、後年、次のような声を寄せている。
「……雨に打たれ、泥濘にまみれ、演技する若者を見ているうちに、私の胸は熱くなり、眼より涙が滂沱と流れてきた。
この若者達は、何かをやろうとする情熱がある。それは功利を超越したものであり、わが国の将来は絶対に明るい」
この感動は、国境も超えて広がった。中国の周恩来(チョウ・エンライ)総理の指示を受けて、創価学会を研究していた側近たちも、この雨の文化祭の記録フィルムを見て、大衆を基盤とした学会への認識を深めていったのである。(「常勝」の章、270ページ)
|