| 男子部編 2020年07月11日 |
苦難こそ誉れ! 師弟こそわが道!! 男子部幹部会で指揮を執る池田先生(1964年2月、東京・台東体育館で) 日蓮仏法は人類救済の指導原理 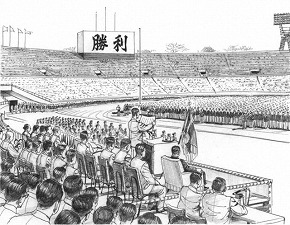 <1961年(昭和36年)11月、男子部の代表10万人が国立競技場に集い、開催された男子部総会で、山本伸一は訴える> 「なぜ、世界も、日本国内も、不幸と悲惨が絶えないのか。それは、日蓮大聖人の大仏法を鑑として拝すれば、すべては明らかであります。 その原因は、いずれの指導者にも、社会を支えゆく民衆にも、確かなる指導理念、哲学がないことにあります。仮に、哲学をもっていても、自他ともの幸福を実現しゆく生命の大哲学ではありません。 そのなかにあって、私どもは、自己の人間革命と、社会、世界の平和を可能にする、完全無欠なる日蓮大聖哲の大生命哲学をもっております。この大生命哲学こそ、人類を救済しゆく、最高の指導原理であるということを、私どもは、声を大にして、叫び続けていこうではありませんか!」 賛同と誓いの大拍手が、競技場の空高く舞った。(中略) 「願わくは、諸君が、それぞれの立場で、全民衆の幸福のため、広宣流布のために、大仏法の正義を証明する、人生の勝利者になっていただきたいことを強く、念願するものでございます。 私は、ただただ、学会の宝であり、人類の希望である、誉れの青年部の諸君の成長と健闘を祈っております。 以上、簡単ではございますが、一言、ごあいさつ申し上げ、講演に代えさせていただきます」(中略) 彼は、哲学不在の時代に、民衆の幸福と人類の平和を築く、真実のヒューマニズムの指導原理が日蓮仏法にあることを、宣言したのである。 (第5巻「勝利」の章、220~221ページ) 創価の後継者は弘教の大闘士に 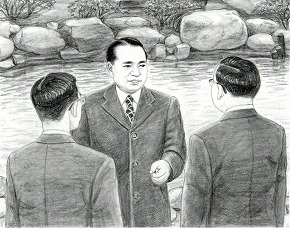 <77年(同52年)3月、福島文化会館(当時)を訪れた伸一は、居合わせた幹部に、学会の後継者が身につけるべき力について語る> 「青年時代に必ず身につけてほしいのは折伏力だ。創価学会は、日蓮大聖人の御遺命である広宣流布を実現するために出現した折伏の団体だもの。その後継者である青年たちが、弘教の大闘士に育たなければ、学会の未来は開けないからね」 大聖人は「日蓮生れし時より・いまに一日片時も・こころやすき事はなし、此の法華経の題目を弘めんと思うばかりなり」(御書1558ページ)と仰せである。その御心を体して、弘教に生き抜くなかに信仰の大道がある。(中略) 折伏は、自身の一生成仏、すなわち絶対的幸福境涯を築く要諦となる仏道修行である。 御書には、「法華経を一字一句も唱え又人にも語り申さんものは教主釈尊の御使なり」(1121ページ)とある。さらに、「末法にして妙法蓮華経の五字を弘めん者は男女はきらふべからず、皆地涌の菩薩の出現に非ずんば唱へがたき題目なり」(1360ページ)と断言されている。 私たちは、勇んで唱題と折伏に励むことによって、仏に連なり、仏の使いの働きをなし、地涌の菩薩となり得るのだ。 つまり、自行化他にわたる信心の実践によって、仏の力が涌現し、地涌の菩薩の大生命が脈動する。(中略) そして、それによって、自身の人間革命、宿命の転換が成し遂げられ、絶対的幸福境涯を築くことができるのだ。また、人びとの苦悩を根本から解決し、崩れざる幸福の道を教える折伏は、最高の慈悲の行である。人間として最も崇高な利他行であり、極善の行為である。 (第25巻「福光」の章、20~21ページ) 命の限り広布に生き抜く「志」を 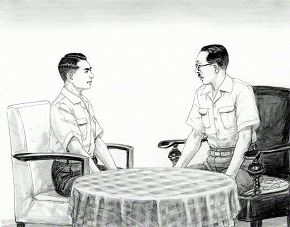 <77年(同52年)10月、北海道・厚田の戸田講堂の開館を祝賀する集いで伸一は、青年部の友に、51年(同26年)7月の男子部結成式前夜、恩師・戸田城聖と交わした師弟の語らいを紹介する> 戸田は、伸一に語っていった。(中略) 「命ある限り、広宣流布に生き抜こうという志をもった人間を、私はつくりたいのだ。(中略) 牧口先生のように、人びとの幸福のために、生涯、正法正義を貫き通す人材を、私は青年部のなかから育てていく。この戸田の弟子であることの“誇り”をもち続け、広宣流布という“大理想”に生き抜こうという人間だ!(中略) 皆の心から、創価の師弟の誇りと、広宣流布の理想に生きようという一念が希薄化してしまえば、学会の未来はない。いや、そうなれば、地涌の菩薩であるとの自覚も失われ、真実の幸福の道も見失ってしまうことになる。学会を、そうさせないために、青年が立つんだ。 伸一! 君は、その事実上の原動力になるんだ。模範になれ! 永遠にだ。班長という一兵卒から戦いを起こし、全軍を率いて、広宣流布の大理想に突き進め! いいな! できるな!」 「はい!」 決意を秘めた伸一の声が響いた。戸田は、鋭い視線を伸一に注いだ。弟子の顔から、微動だにしない広宣流布への信念を見て取った戸田は、口元をほころばせた。 「頼んだぞ! 万人の幸福を築け! そのために学会は、後世永遠に広宣流布を、立正安国をめざして進んでいくんだ。 今夜の二人の語らいが、事実上の男子青年部の結成式だよ」 (第26巻「厚田」の章、40~42ページ) 多忙の中での挑戦が自身を錬磨 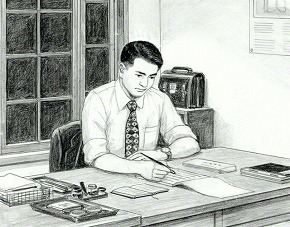 <51年(同26年)9月、御書講義の講師として埼玉・川越地区に派遣された伸一は、仕事が忙しく学会活動の時間が取れないと悩む青年を励ます> 「私もそうです。どうやって学会活動の時間をつくりだそうかと、悩み抜いています。(中略) 青年時代に職場の第一人者をめざして懸命に働いていれば、忙しいに決まっています。(中略) 多忙ななかで、いかに時間をつくりだすかが既に戦いなんです。少しでも早く、見事に仕事を仕上げて活動に出ようと、必死に努力することから、仏道修行は始まっています。自分の生命が鍛えられているんです。 この挑戦を重ねていけば、凝縮された時間の使い方、生き方ができるようになります。 平日は、どうしても動けないのなら、日曜などに、一週間分、一カ月分に相当するような充実した活動をするという方法もあります。 たとえ会合に出られないことがあっても、広宣流布に生き抜こうという信心を、求道心を、一歩たりとも後退させてはなりません。 『極楽百年の修行は穢土の一日の功徳に及ばず』(御書329ページ)との御文がありますが、大変な状況のなかで、信心に励むからこそ、それだけ功徳も大きいんです。 戸田先生は、よく『青年は苦労せよ。苦労せよ』『悩みなさい。うんと悩みなさい』とおっしゃいます。(中略) 私も、その先生のご指導を生命に刻んで、歯を食いしばりながら挑戦しています。 君には、今の大変な状況のなかで、『こうやって学会活動をやり抜いた』『こうやって職場の大勝利者になった』という実証を示して、多くの男子部員に、その体験を語れるようになってほしいんです」 (第26巻「奮迅」の章、399~400ページ) |