|
信心に励む人は成仏の軌道に

<1965年(昭和40年)1月、山本伸一は大阪から急きょ、鳥取の米子へ向かう。若き支部長の事故死によって多くの同志の胸に生じた、信心への疑いと迷いを晴らすためであった>
真の信仰者として広宣流布に邁進している人は、いかなるかたちで命を終えようとも、成仏は間違いない。
初期の仏典には、次のような話がある。
――摩訶男(マハーナーマ)という、在家の信者がいた。彼は、もし、街の雑踏のなかで、三宝への念を忘れている時に、災難に遭って命を失うならば、自分はどこで、いかなる生を受けるのかと、仏陀に尋ねる。
すると、仏陀は言う。
「摩訶男よ、たとえば、一本の樹木があるとする。その樹は、東を向き、東に傾き、東に伸びているとする。もしも、その根を断つならば、樹木は、いずれの方向に、倒れるであろうか」
摩訶男は答えた。
「その樹木が傾き、伸びている方向です」
仏陀は、仏法に帰依し、修行に励んでいるものは、たとえ、事故等で不慮の死を遂げたとしても、法の流れに預かり、善処に生まれることを教えたのである。
また、日蓮大聖人は、南条時光に、弟の死に際して与えられたお手紙で、「釈迦仏・法華経に身を入れて候いしかば臨終・目出たく候いけり」(御書1568ページ)と仰せになっている。信心に励んだ人の、成仏は間違いないとの御指南である。(中略)
彼は、十八日、空路、大阪から米子に向かった。最も大変なところへ、自ら足を運ぶ――それが伸一の、指導者としての哲学であった。
(「言論城」の章、20~22ページ)
学会活動は生命を鍛錬する場
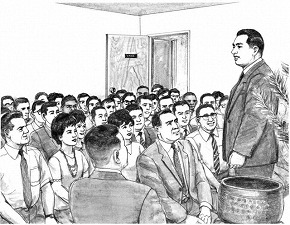
<伸一は8月15日、アメリカのロサンゼルスで行われた海外初の野外文化祭に出席。翌日の懇談会で、自身の幸福を築くための学会活動であることを確認する>
「今回の文化祭は、(中略)極めて大変な条件のなかでの文化祭であったと思う。
途中で、やめてしまおうかと思った人もいるかもしれない。だが、そんな自分と戦い、懸命に唱題し、それぞれの分野で、真剣に努力されてきた。
まず、広宣流布の大きな布石となる文化祭のための唱題が、努力が、献身が、そのまま、大功徳、大福運となりゆくことは、絶対に間違いありません。これが妙法の因果の力用です。
また、皆さんは、文化祭を大成功させるために、不可能と思われた限界の壁、困難の壁を、一つ一つ破ってこられた。そして、この文化祭を通して、自信と、信心への揺るぎない確信をつかまれたことと思う。
実は、それが何よりも、大事なことなんです。
人生には、さまざまな試練がある。病に倒れることもあれば、仕事で行き詰まることもある。
その時に、悠々と乗り越えていくためには、生命の鍛錬が必要です。精神の骨格となる、信心への大確信が必要なんです。
この文化祭に全力で取り組み、唱題を根本に、あらゆる困難を克服してこられた皆さんは、“仏法に行き詰まりはない”との体験をつかまれたと思います。
こうした体験を、どれだけ積んできたかによって、仏法への揺るぎない大確信が育まれ、何があっても負けることのない、強い自身の生命が鍛え上げられていきます。
そのための『場』となるのが、学会活動です。また、文化祭でもあります。つまり、自分の幸福の礎を築いていくための活動なんです」
(「幸風」の章、133~134ページ)
民衆による民衆のための宗教
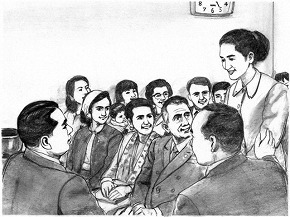
<10月、フランスのパリを訪れた伸一は、ヨーロッパの拠点となる事務所の開所式に参加。世界広布の先駆を切る女性たちを励ましながら、民衆こそが広宣流布の主役であることを思う>
アメリカでも、東南アジアでも、日蓮仏法を弘めてきたのは、キリスト教のような宣教師ではなかった。
世界広布を担ってきたのは、“衣の権威”に身を包んだ僧侶たちではなく、在家である創価学会の、名もなき会員たちであった。しかも、その多くは女性たちである。
なんの後ろ盾もない、不慣れな土地で、日々の生活と格闘しながら、言葉や風俗、習慣の違いを超えて、人びとの信頼と友情を育み、法を伝えてきたのだ。誤解や偏見による、非難もあったにちがいない。まさに、忍耐の労作業といってよい。
宗教の歴史には、武力や権力、財力などを背景にした布教も少なくなかった。しかし、それでは、どこまでも対話主義を貫き、触発と共感をもって布教してきた、日蓮大聖人の御精神を踏みにじることになる。「力」に頼ることなく、民衆が主役となって布教を推進してきたところに、日蓮仏法の最大の特徴があるといってよい。
また、それ自体が、「民衆のための宗教」であることを裏付けている。
伸一は、遠く異国の地にあって、広宣流布に生き抜こうとする、健気なる同志に、仏を見る思いがしてならなかった。
(「新航路」の章、224~225ページ)
広布誓願の祈りが病魔を克服
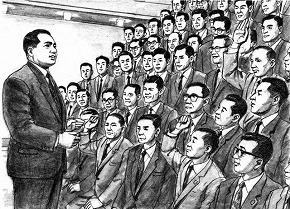
<伸一は11月、関西本部新館で奈良本部の同志と記念撮影に臨む。そこで、“病気の宿業は乗り越えられるのか”との質問に答える>
「どんなに深い宿業だろうが、必ず断ち切っていけるのが、日蓮大聖人の大仏法です。(中略)
本来、その宿業は少しずつしか出ないために、何世にもわたって、長い間、苦しまなければならない。
しかし、信心に励むことによって、これまでの宿業が、一気に出てくる。そして、もっと重い苦しみを受けるところを、軽く受け、それで宿業を転換できる。『転重軽受』です。(中略)
御本尊への、深い感謝の一念が、大歓喜の心を呼び覚まします。そして、この大歓喜が大生命力となっていくんです。
唱題するにしても、ただ漫然と祈っていたり、御本尊への疑いを心にいだいて祈っていたのでは、いつまでたっても、病魔を克服することはできません。
大事なことは、必ず、病魔に打ち勝つぞという、強い強い決意の祈りです。そして、懺悔滅罪の祈りであり、罪障を消滅してくださる御本尊への、深い深い感謝の祈りです。
胃が癌に侵されているというのなら、唱題の集中砲火を浴びせるような思いで、題目を唱えきっていくんです。
さらに、重要なことは、自分は広宣流布のために生き抜くのだと、心を定めることです。そして、“広布のために、自在に働くことのできる体にしてください”と、祈り抜いていくんです。広宣流布に生き抜く人こそが、地涌の菩薩です。法華経の行者です。広布に生きる時には、地涌の菩薩の大生命が全身に脈動します。その燦然たる生命が、病を制圧していくんです」
(「桂冠」の章、300~302ページ)
創価教育の誓い
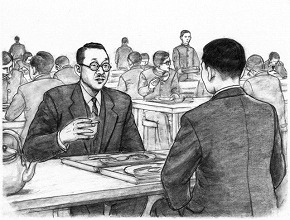
<1965年11月、創価大学設立審議会が発足。牧口常三郎初代会長と戸田城聖第2代会長の悲願の実現へ、本格的な準備が始まる。「桂冠」の章には、山本伸一が両会長の構想実現を誓う場面が描かれている>
伸一は、師の戸田から大学設立の構想を聞かされた折のことが、一日として頭から離れなかった。
――それは、戸田が経営していた東光建設信用組合が、経営不振から業務停止となり、再起を期して設立した新会社の大東商工が、細々と回転し始めようとしていた、一九五〇年(昭和二十五年)の十一月十六日のことであった。
戸田のもとにいた社員たちも、給料の遅配が続くと、一人、また、一人と、恨み言を残して去っていった。伸一も、オーバーなしで冬を迎えねばならぬ、秋霜の季節であった。
この日、伸一は、西神田の会社の近くにある、日本大学の学生食堂で、師の戸田と昼食をともにした。安価な学生食堂にしか行けぬほど、戸田城聖の財政は逼迫していた。
彼にとっては、生きるか死ぬかの、戦後の最も厳しい“激浪の時代”である。
しかし、戸田は泰然自若としていた。彼は、学生食堂へ向かう道々、伸一に、壮大な広宣流布の展望を語るのであった。
食堂には、若々しい談笑の声が響いていた。
戸田は、学生たちに視線を注ぎながら、微笑みを浮かべて言った。
「伸一、大学をつくろうな。創価大学だ」
伸一が黙って頷くと、戸田は、彼方を仰ぐように目を細めて、懐かしそうに語り始めた。
「間もなく、牧口先生の七回忌だが、よく先生は、こう言われていた。
『将来、私が研究している創価教育学の学校を必ずつくろう。もし、私の代に創立できない時は、戸田君の代でつくるのだ。小学校から大学まで、私の構想する創価教育の学校をつくりたいな』と……」
ここまで語ると、戸田は険しい顔になった。
「しかし、牧口先生は、牢獄のなかで生涯を閉じられた。さぞ、ご無念であったにちがいない。私は、構想の実現を託された弟子として、先生に代わって学校をつくろうと、心に誓ってきた。牧口先生の偉大な教育思想を、このまま埋もれさせるようなことがあっては、絶対にならない。そんなことになったら、人類の最高最大の精神遺産をなくしてしまうようなものだ。
人類の未来のために、必ず、創価大学をつくらねばならない。しかし、私の健在なうちにできればいいが、だめかもしれない。伸一、その時は頼むよ。世界第一の大学にしようじゃないか!」
この時の戸田の言葉を、伸一は、決して、忘れることはなかったのである。
だが、既に、その戸田も世を去っていた。創価教育の学校の設立は、牧口から戸田へ、戸田から伸一へと託され、今、すべては、彼の双肩にかかっていたのである。
伸一は、先師・牧口の、そして、恩師・戸田の構想の実現に向かい、いよいよ第一歩を踏み出せたことが嬉しかった。(中略)
師匠が描いた構想を現実のものとし、結実させてこそ、まことの弟子である。その不断の行動と勝利のなかにのみ、仏法の師弟の、尊き不二の大道がある。金色に輝く、共戦の光の道がある。
(293~296ページ)
|