|
人間の蘇生こそ平和の原点

<1960年(昭和35年)10月、山本伸一はハワイの座談会で、アメリカ人と結婚し、孤独を抱えながら暮らす日本人女性を励ます>
「あなた以外にも、このハワイには、同じような境遇の日本女性がたくさんいると思います。
あなたが、ご家族から愛され、慕われ、太陽のような存在になって、見事な家庭を築いていけば、日本からやってきた婦人たちの最高の希望となり、模範となります。みんなが勇気をもてます。
あなたが幸せになることは、あなた一人の問題にとどまらず、このハワイの全日本人女性を蘇生させていくことになるんです。
だから、悲しみになんか負けてはいけません。強く、強く生きることですよ。そして、どこまでも朗らかに、堂々と胸を張って、幸せの大道を歩いていってください。さあ、さあ、涙を拭いて」
伸一の指導は、婦人の心を、激しく揺さぶらずにはおかなかった。慈愛ともいうべき彼の思いが、婦人の胸に熱く染みた。彼女は、ハンカチで涙をぬぐい、深く頷くと、ニッコリと微笑んだ。
「はい、負けません」
その目に、また涙が光った。それは、新たな決意に燃える、熱い誓いの涙であった。
伸一の平和旅は、生きる希望を失い、人生の悲哀に打ちひしがれた人びとに、勇気の灯を点じることから始まったのである。それは、およそ世界の平和とはほど遠い、微細なことのように思えるかもしれない。
しかし、平和の原点は、どこまでも人間にある。一人ひとりの人間の蘇生と歓喜なくして、真実の平和はないことを、伸一は知悉していたのである。
(「旭日」の章、59~60ページ)
学会の理解者に最大の敬意
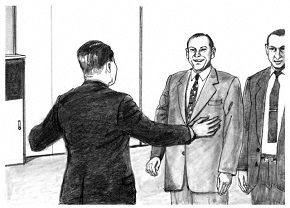
<サンフランシスコで伸一は、信心に励む妻を支える未入会の夫への感謝を語る>
「信心をしていないのに、学会をよく理解し、協力してくれる。これほどありがたいことはない。私は、その尽力に、最大の敬意を表したいんです。
みんなは、ただ信心しているか、していないかで人を見て、安心したり、不安がったりする。しかし、それは間違いです。その考え方は仏法ではありません。
信心はしていなくとも、人格的にも立派な人はたくさんいる。そうした人たちの生き方を見ると、そこには、仏法の在り方に相通じるものがある。また、逆に信心はしていても、同志や社会に迷惑をかけ、学会を裏切っていく人もいます。
だから、信心をしているから良い人であり、していないから悪い人だなどというとらえ方をすれば、大変な誤りを犯してしまうことになる。いや、人権問題でさえあると私は思っているんです」
伸一の思考のなかには、学会と社会の間の垣根はなかった。仏法即社会である限り、仏法者として願うべきは、万人の幸福であり、世界の平和である。
また、たとえば広い裾野をもつ大山は容易に崩れないが、断崖絶壁はもろく、崩れやすいものだ。同様に、盤石な広布の建設のためには、大山の裾野のように、社会のさまざまな立場で、周囲から学会を支援してくれる人びとの存在が大切になってくる。
更に、そうした友の存在こそが、人間のための宗教としての正しさの証明にほかならないことを、彼は痛感していたのである。
(「新世界」の章、118~119ページ)
「地涌の菩薩」の使命を自覚

<シカゴの座談会で伸一は、人種差別に苦しみ、自分のルーツに縛られてきた黒人の青年に、「地涌の菩薩」の自覚に立つよう促す>
「仏法では、私たちは皆、『地涌の菩薩』であると教えています。
『地涌の菩薩』とは、久遠の昔からの仏の弟子で、末法のすべての民衆を救うために、広宣流布の使命を担って、生命の大地から自らの願望で出現した、最高の菩薩のことです。
もし、ルーツと言うならば、これこそが、私たちの究極のルーツです。つまり、私たちは、いや、人間は本来、誰もが社会の平和と幸福を実現していく使命をもった久遠の兄弟なんです。
自己自身の立脚点をどこに置くかによって、人生の意味は、まったく異なってきます。たとえば、緑の枝を広げた大樹は、砂漠や岩の上には育ちません。それは、肥沃な大地にこそ育つものです。
同じように、豊かな人間性を開花させ、人生の栄冠が実る人間の大樹になるには、いかなる大地に立って生きていくかが大事になります。その立脚点こそ、『地涌の菩薩』という自覚なんです。
この大地は普遍であり、人種や民族や国籍を超え、すべての人間を蘇生させ、文化を繁茂させます。その地中には、慈悲という清らかな利他の生命の泉が湧いています。皆がこの『地涌の菩薩』の使命を自覚し、行動していくならば、真実の世界の平和と人間の共和が築かれていくことは間違いありません」
(「錦秋」の章、184~185ページ)
最高の宝石は自身の中に
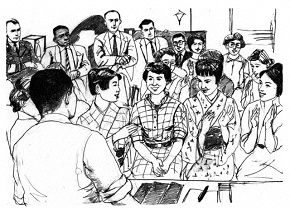
<ニューヨークの座談会を訪れた伸一は、信心の確信を持てない婦人たちを温かく包み込むように指導>
「信心を貫くならば、一人も漏れなく、幸福になれます。現に、日本では、百万人を超える同志が幸せになっています。それが最大の証明ではないですか。仏典には、こんな話が説かれています。
昔、ある男が、親友の家で酒を振る舞われ、酔って眠ってしまった。親友は、この男が決して生活に困り、嘆くことのないように、寝ている間に、最高の高価な宝石を衣服の裏に縫いつけてあげた」
参加者は、吸い込まれるように、伸一の話に聞き入っていった。
「……やがて、男は別の土地に行き、おちぶれて食べるにも事欠くほど貧乏になってしまった。しかし、自分の衣服に、そんな高価な宝石が縫いつけられていることなど、全く気づかなかった。おちぶれた果てに、男は親友と再会する。親友は、男の衣服に、高価な宝石を縫いつけたことを教える。その宝石のことを知った男が、幸せになったのはいうまでもありません。
これは、法華経に説かれた『衣裏珠の譬』という説話です。最高の宝石とは、皆さんの心にある『仏』の生命のことです。御本尊に唱題し、広宣流布のために戦うことによって、その『仏』の生命を引き出し、最高の幸福境涯を築くことができる。
しかし、せっかく信心をしながら、それがわからずに、ただ悲しみに沈んでいるとしたなら、この説話の男と同じようなものです」
(「慈光」の章、228~229ページ)
“広布誓願”の決意の祈りを
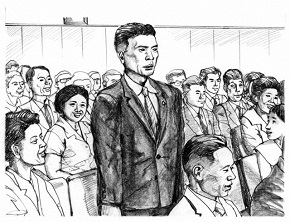
<ブラジルのサンパウロの座談会で伸一は、農業を営み、不作に悩む壮年の質問に答える>
「仏法というのは、最高の道理なんです。ゆえに、信心の強盛さは、人一倍、研究し、工夫し、努力する姿となって表れなければなりません。そして、その挑戦のエネルギーを湧き出させる源泉が真剣な唱題です。それも“誓願”の唱題でなければならない」
「セイガンですか……」
壮年が尋ねた。皆、初めて耳にする言葉であった。
伸一が答えた。
「“誓願”というのは、自ら誓いを立てて、願っていくことです。祈りといっても、自らの努力を怠り、ただ、棚からボタモチが落ちてくることを願うような祈りもあります。それで良しとする宗教なら、人間をだめにしてしまう宗教です。
日蓮仏法の祈りは、本来、“誓願”の唱題なんです。その“誓願”の根本は広宣流布です。
つまり、“私は、このブラジルの広宣流布をしてまいります。そのために、仕事でも必ず見事な実証を示してまいります。どうか、最大の力を発揮できるようにしてください”という決意の唱題です。これが私たちの本来の祈りです」
(「開拓者」の章、294~295ページ)
恩師との胸中の語らい
1960年(昭和35年)10月2日、山本伸一は初の海外平和旅に出発。最初の訪問地ハワイに向かう機中で、彼は恩師・戸田先生との語らいを思い起こした。

羽田の東京国際空港で、見送る学会員に手を振る池田先生(1960年10月2日)
伸一は、静かに胸に手をあてた。彼の上着の内ポケットには、恩師・戸田城聖の写真が納められていた。彼は、戸田が逝去の直前、総本山で病床に伏しながら、メキシコに行った夢を見たと語っていたことが忘れられなかった。
――あの日、戸田は言った。
「待っていた、みんな待っていたよ。日蓮大聖人の仏法を求めてな。行きたいな、世界へ。広宣流布の旅に……。伸一、世界が相手だ。君の本当の舞台は世界だよ。世界は広いぞ」
伸一は、戸田が布団のなかから差し出した手を、無言で握り締めた。
すると、戸田は、まじまじと伸一の顔を見つめ、力を振り絞るように言った。
「……伸一、生きろ。うんと生きるんだぞ。そして、世界に征くんだ」
戸田の目は鋭い光を放っていた。伸一は、その言葉を遺言として胸に刻んだ。
彼は、亡き恩師に代わって、弟子の自分が世界広布の第一歩を印すことを思うと、熱い感慨が込み上げてならなかった。
彼が初の海外訪問の出発の日を十月二日と決めたのも、二日が戸田の命日にあたるからであった。伸一には、「世界に征くんだ」と語った戸田の思いが痛いほどわかった。
(「旭日」の章、14ページ)
|