|
核軍縮義務の履行に向け
安全保障の見直しを推進
パンデミックが知らしめた教訓
第三の課題は、核兵器の廃絶を何としても成し遂げることです。
そのために、二つの提案をしたい。
一つ目は、核兵器に依存した安全保障からの脱却を図るためのものです。
今月3日、核保有国のアメリカ、ロシア、中国、イギリス、フランスの5カ国の首脳が、核戦争の防止と軍拡競争の回避に関する共同声明を発表しました。
さまざまな受け止め方もありますが、「核戦争に勝者はなく、決して戦ってはならない」との精神を確認し、軍事的対立の回避を共に追求する意思を表明したもので、積極的な行動につなげることが望まれます。
このような“自制”の重要性を踏まえた共同声明を基礎としながら、核拡散防止条約(NPT)の第6条で定められた核軍縮義務の履行に向けて、核保有5カ国が具体的措置を促進するための決議を、国連安全保障理事会で採択することを呼びかけたい。
そして、年内に開催予定のNPT再検討会議での合意として、「核兵器の役割低減に関する首脳級会合」の開催を最終文書に盛り込み、NPTの枠外で核兵器を保有する国の参加も呼びかけながら、大幅な核軍縮を進めることを訴えたい。
コロナ危機が続く中で、世界の軍事費は増大しており、核兵器についても1万3000発以上が残存する中、その近代化は一向に止まらず、核戦力の増強が進む恐れがあると懸念されています。
またコロナ危機は、核兵器を巡る新たなリスクを顕在化させました。核保有国の首脳が相次いで新型コロナに感染し、一時的に執務を離れざるを得なかったほか、原子力空母や誘導ミサイル駆逐艦で集団感染が起こるなど、指揮系統に影響を及ぼしかねない事態が生じたからです。

昨年6月、スイスのジュネーブで行われた、アメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領との首脳会談(EPA=時事)。会談後に発表された共同声明では、「核戦争に勝者はなく、決して戦ってはならない」との精神が再確認された
そして何より、コロナ危機の発生が世界に知らしめた重大な教訓があります。
国連の中満泉・軍縮担当上級代表は、昨年9月に行った核問題を巡るスピーチで、その教訓についてこう述べていました。
「新型コロナのパンデミックの教訓として、一見、起こりそうにない出来事が、実際に前触れもなく起こり、地球規模で壊滅的な影響を及ぼしうるということがあります」と。
私もこの教訓を踏まえて、“核兵器による惨劇は起きない”といった過信を抱き続けることは禁物であると強く警告を発したい。
中満上級代表がそこで強調していたように、広島と長崎への原爆投下以降、核兵器が使用されずに済んできたのは、それぞれの時代で最悪の事態を防いできた人々の存在と何らかの僥倖があったからでした。
しかし、「国際環境が流動化し、ガードレールは腐食しているか、もしくは全く存在していない」という現在の世界において、人的な歯止めや僥倖だけに頼ることは、もはや困難になってきているというのです。
実際、核軍縮に関する二国間の枠組みは、昨年2月に米ロ両国が延長に合意した新戦略兵器削減条約(新START)〈注6〉だけしか残されていません。
今月に開催予定だったNPT再検討会議は、新型コロナの影響で延期され、8月に開催することが検討されています。
前回(2015年)の会議では最終文書が採択されずに閉幕しましたが、その轍を踏むことがあってはなりません。NPTの前文に記された“核戦争の危険を回避するためにあらゆる努力を払う”との誓いに合致する具体的な措置に合意するよう、強く望みたい。
1985年の米ソ首脳の声明の意義
核保有5カ国の首脳が共同声明で再確認した、「核戦争に勝者はなく、決して戦ってはならない」との精神は、冷戦時代の1985年11月にジュネーブで行われた、アメリカのレーガン大統領とソ連のゴルバチョフ書記長による首脳会談で打ち出されたものでした。
この精神の重要性は、昨年6月の米ロ首脳会談における声明でも言及されたものでしたが、核時代に終止符を打つために何が必要となるのかについて討議する機会を国連安全保障理事会で設けて、その成果を決議として採択し、時代転換の出発点にすべきだと、私は考えるのです。
1985年の米ソ首脳の声明は、両国のみならず、全人類にとって有益となる核軍縮交渉の始まりを画したものとして高く評価されていますが、ゴルバチョフ氏は当時を振り返ったインタビューの中で、核軍縮に踏み切った思いについて、こう語っていました。
「これくらいでは山は崩れないだろうと思って、頂上から石をひとつ、ころがしてみたとする。ところが、その一石が引き金になって山じゅうの石がころがり出すと、山が崩れてしまう。核戦争も一緒で、一発のミサイル発射で全部が動き出してしまう。現在、戦略核の制御・管理は、完全にコンピューターに頼っていると言っても過言ではない。核兵器数が多ければ多いほど、偶発核戦争の可能性も大きくなる」(吉田文彦『核のアメリカ』岩波書店)

ゴルバチョフ元ソ連大統領と9度目の語らい。“大事なのは、「歴史がどうなっていくか」ではなく、「歴史をどう変えていくか」である”との認識を共有しつつ、人類の希望の未来を開くために、対話をさらに深めていくことが約し合われた(2007年6月、八王子市の東京牧口記念会館で)
今なお核開発はやまず、一つまた一つと生み出される他国への対抗手段は、「これくらいでは山は崩れないだろう」との見込みで、進められているのかもしれません。
しかし、脅威の対峙による核抑止を続ける限り、極めて危うい薄氷の上に立ち続けなければならない状態から、いつまでも抜け出せないという現実に、核保有国と核依存国は真正面から向き合うべきではないでしょうか。
この点に関し、ゴルバチョフ氏が、私との対談でも次のように強調していたことを思い起こします。
「核兵器が、もはや安全保障を達成する手段となり得ないことは、ますます明確になっています。実際、年を経るごとに、核兵器はわれわれの安全をより危ういものとしているのです」(「新世紀の曙」、「潮」2009年3月号所収)と。
核兵器の使用を巡るリスクが高まっている現状を打開するには、核依存の安全保障に対する“解毒”を図ることが、何よりも急務となると思えてなりません。
「核兵器の全面的な不使用」を目指し
首脳級会合を広島で開催
核抑止政策の主眼は、他国に対して核兵器の使用をいかに思いとどまらせるかにあるといわれます。しかしそこには、核使用を防ぐとの理由を掲げながらも、核抑止の態勢をとる前提として、核兵器を自国が使用する可能性があることを常に示し続けねばならないという矛盾があります。
その矛盾を乗り越えて、自国の安全保障政策から核兵器を外すためには、国際社会への働きかけを含め、どのような新しい取り組みが自国に必要となるのかを、真摯に見つめ直すことが求められるのです。
自国の安全保障がいかに重要であったとしても、対立する他国や自国に壊滅的な被害をもたらすだけにとどまらず、すべての人類の生存基盤に対して、取り返しのつかない惨劇を引き起こす核兵器に依存し続ける意味は、一体、どこにあるというのか――。
この問題意識に立って、他国の動きに向けていた眼差しを、自国にも向け直すという“解毒”の作業に着手することが、NPTの前文に記された“核戦争の危険を回避するためにあらゆる努力を払う”との共通の誓いを果たす道ではないかと訴えたいのです。
NPT第6条が定められた意味
NPTの目的は、核兵器の脅威が対峙し合う状況を“人類の逃れがたい運命”として固定することにはないはずです。その根本的な解消を図らねばならないとの共通認識があったからこそ、NPTの重要な柱として、第6条に核軍縮義務が明確に組み込まれたことを忘れてはなりません。
冷戦時代とは異なり、緊急事態が生じても、リアルタイムの映像で互いの表情を見ながら、首脳同士が対話を行うことができる時代が到来したにもかかわらず、核兵器を即時発射できる態勢を維持し、互いの出方を疑心暗鬼のままで探り合う状態が続いています。
核保有5カ国による共同声明では、「我々の核兵器は、いずれも互いの国を標的とせず、また、他のいかなる国も標的にしていないことを再確認する」と宣言されていました。
今こそ、核保有国はこの“自制”を基礎に安全保障政策の本格的な転換に踏み出し、冷戦時代から現在まで存在してきた核兵器の脅威を取り去るべき時です。
その環境づくりのために、安全保障政策における核兵器の役割低減をはじめ、紛争や偶発的な核使用のリスクを最小限に抑えることや、新規の核兵器の開発を中止することなどについて、検討を開始する必要がありましょう。
明年には、日本でG7サミットが開催されます。その時期に合わせる形で、広島で「核兵器の役割低減に関する首脳級会合」を行い、他の国々の首脳の参加も得ながら、これらの具体的な措置を進めるための方途について集中的に討議してはどうでしょうか。
今月21日、日本とアメリカが、NPTに関する共同声明を発表しました。
そこでは、「世界の記憶に永遠に刻み込まれている広島及び長崎への原爆投下は、76年間に及ぶ核兵器の不使用の記録が維持されなければならないということを明確に思い起こさせる」と述べた上で、政治指導者や若者に対し、核兵器による悲劇への理解を広げるため、広島と長崎への訪問が呼びかけられていました。
私も以前から、政治指導者の被爆地訪問の重要性を訴え続けてきましたが、広島での首脳級会合の開催は、その絶好の機会になると思えてなりません。
首脳級会合では、核兵器のない世界の実現に向けた「核兵器の全面的な不使用」の確立を促すための環境整備とともに、私が2020年の提言で言及した、「核関連システムに対するサイバー攻撃」や「核兵器の運用におけるAI導入」の禁止についても討議することを求めたい。その一連の取り組みを通し、NPT第6条の核軍縮義務を履行するための交渉を本格化させ、核廃絶への流れを不可逆的なものにすることを、強く望むものです。
核兵器禁止条約の普遍化こそ
持続可能な地球社会の礎
核禁条約の会合で日本が積極貢献を
核問題に関する二つ目の提案は、核兵器禁止条約に関するものです。
3月にオーストリアのウィーンで行われる条約の第1回締約国会合に、日本をはじめとする核依存国と核保有国がオブザーバー参加するよう、改めて強く呼びかけたい。そして締約国会合で、条約に基づく義務の履行や国際協力を着実に推し進めるための「常設事務局」の設置を目指すことを提唱したい。
すでに、条約に参加していない国の間で、スイス、スウェーデン、フィンランドに加えて、北大西洋条約機構(NATO)の加盟国であるノルウェーとドイツも、オブザーバー参加の意向を示しています。
NATOでは、核兵器への対応について加盟国が独自の道を歩むことを認めてきた歴史があり、一方の核兵器禁止条約においても、核保有国との同盟関係そのものを禁止する規定はありません。

2017年7月、ニューヨークの国連本部で行われた核兵器禁止条約の交渉会議。122カ国の賛成を得て、条約が採択された。SGIとしても、交渉会議に2回にわたって作業文書を提出するなどの努力を重ねる中で、戸田第2代会長の「原水爆禁止宣言」から60周年の節目の年に条約の採択が実現した
世界の都市が条約への支持を表明し、自国の条約への参加を促す、ICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)の「都市アピール」にNATO加盟国の多くの都市が加わる中、締約国会合にノルウェーとドイツが参加する意義は極めて大きいといえましょう。
このアピールには、核兵器を保有するアメリカ、イギリス、フランス、インドの都市のほか、日本の広島と長崎も加わっています。
締約国会合で予定されるテーマには、「核使用や核実験による被害者支援」と「汚染地域の環境改善」も含まれており、日本が議論に参加して、広島と長崎の被害の実相とともに、福島での原発事故の教訓を分かち合う貢献をしていくべきではないでしょうか。
ハンブルク大学平和研究・安全保障政策研究所のオリバー・マイヤー主任研究員は、ドイツの参加表明を「多国間主義と核軍縮の強化に貢献できる」と評価した上で、核保有国と非保有国の「橋渡し」役を目指す日本が参加する意義について、こう述べていました。
「『橋渡し』は、橋の両側に自ら出向いて議論してこそ、可能なはず。被爆国にしかない役割を担うことができる」(「中国新聞」2021年12月6日付朝刊)と。
日本は2017年から、核保有国と非保有国の識者を交えた「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」と、同会議をフォローアップする会合を行っており、その成果を報告して、建設的な議論に資する意義も大きいと思います。こうした努力を尽くしながら、日本は早期の批准を目指すべきだと訴えたいのです。

核拡散防止条約(NPT)再検討会議の第3回準備委員会に合わせて、2019年4月、ニューヨーク市内で行われた核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)の市民会議。SGIの代表が出席したほか、学生ら若い世代も多く参加した
かつて、クラスター爆弾禁止条約の第1回締約国会合が行われた時、34カ国がオブザーバー参加し、その多くが最終的に締約国になった事例もありました。
核兵器禁止条約についても同様に、より多くの国がオブザーバー参加を果たし、核兵器の廃絶を何としても成し遂げようとする締約国と市民社会の真摯な取り組みに接する中で、条約が切り開く“新しい世界の地平”を共に見つめ直すことが重要だと考えます。
核兵器禁止条約は、軍縮条約の域にとどまるものではなく、壊滅的な惨害を食い止める「人道」と、世界の民衆の生存の権利を守る「人権」の規範が骨格に据えられた条約です。
また、先に気候変動問題を論じた際に触れた「グローバル・コモンズ」の観点に照らせば、「人類全体の平和」や「未来世代の生存基盤となる地球の生態系」を守り抜く礎として、欠かせない条約にほかなりません。
その条約の真価を鑑みた上で、核兵器に依存した安全保障が、現在のみならず未来の世界にどのような影響を及ぼしかねないのかについて、胸襟を開いた対話をすべきです。
ウィーンでの締約国会合を契機に、立場の違いを超えた対話を重ねる中で、締約国の拡大とともに、直ちに署名や批准に踏み切ることができなくても、条約の真価を前向きに認める国々の輪が広がっていけば、“核時代に終止符を打つための力”に結実していくと信じてやまないのです。
その意味からも私は、核兵器禁止条約のための「常設事務局」の設置を実現させて、条約の理念と義務を普遍化させるための“各国と市民社会との連合体の中軸”としていくことを呼びかけたいと思います。
これまでSGIでは、2007年に開始した「核兵器廃絶への民衆行動の10年」を通し、ICANなどの団体と協力して、核兵器禁止条約の採択を後押しするとともに、その実現を果たした翌年(2018年)からは、「民衆行動の10年」の第2期の活動を進めてきました。
第2期では、市民社会の手で条約の理念を普及させることに力を入れており、本年もその流れをさらに強めていきたい。グローバルな民衆の支持こそが、条約の実効性を高める基盤になると確信するからです。
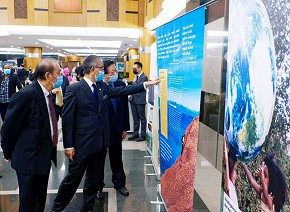
2020年9月から10月にかけて、マレーシアの外務省で行われた「核兵器なき世界への連帯」展(首都クアラルンプールの近郊で)。SGIと核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)が共同制作した展示は、21カ国90都市以上で行われてきた
すべてを一瞬で無にする非人道性
思い返せば、激動の20世紀を通して何度も危機の現場に身を置いてきた、経済学者のガルブレイス博士が、この課題だけは皆で一致して取り組まねばならないと力説していたのが、核兵器の脅威を取り除くことでした(『ガルブレイス著作集』第9巻、松田銑訳、TBSブリタニカを引用・参照)。
博士が自叙伝の結びで、「回想録の著者が、どこで公事に関する筆をおくかを判断するのは難しいものである」と述べつつ、あえて締めくくりに書き留めたのは、専門とする経済の話ではありませんでした。
広島と長崎に原爆が投下された年の秋に、日本を初訪問して以来、「一度もその教訓を忘れたことはない」と語る核兵器の問題だったのです。
そこには、1980年に博士が行った演説の一節が綴られています。
「もし我々が核兵器競争の抑制に失敗すれば、我々がこの数日間議論してきた、他の一切の問題は無意味となるでありましょう。
公民権の問題もなくなるでしょう。公民権の恩恵を被る人間がいなくなるから。
都市荒廃の問題もなくなるでしょう。わが国の都市は消え失せてしまうから」
「他の一切の問題については、意見が分れても、それは差支えありません。
しかし次の一点については、合意しようではありませんか――我々が、全人類の頭上を覆う、この核の恐怖を除くために力を尽すと、アメリカ全国民、全同盟国、全人類に誓うということについては」と。
ガルブレイス博士が剔抉していたように、核兵器の非人道性は、その攻撃がもたらす壊滅的な被害だけにとどまりません。
どれだけ多くの人々が、“社会や世界を良くしたい”との思いで長い歳月と努力を費やそうと、ひとたび核攻撃の応酬が起これば、すべて一瞬で無に帰してしまう――。あまりにも理不尽というほかない最悪の脅威と、常に隣り合わせに生きることを強いられているというのが、核時代の実相なのです。

戸田第2代会長の「原水爆禁止宣言」60周年を迎えた2017年9月に、その発表の場となった横浜市・三ツ沢の競技場を訪れたSGIの友。戸田会長の遺訓をかみしめながら、「戦争と核兵器のない世界」の建設を誓い合った
現代文明の一凶を取り除く挑戦を!
私どもが進めてきた核廃絶運動の原点は、戸田第2代会長が1957年9月に行った「原水爆禁止宣言」にあります。
核保有国による軍拡競争が激化する中、その前月にソ連が大陸間弾道弾(ICBM)の実験に初成功し、地球上のどの場所にも核攻撃が可能となる状況が、世界の“新しい現実”となってまもない時期でした。
この冷酷な現実を前にして戸田会長は、いかなる国であろうと核兵器の使用は絶対に許されないと強調し、核保有の正当化を図ろうとする論理に対し、「その奥に隠されているところの爪をもぎ取りたい」(『戸田城聖全集』第4巻)と、語気強く訴えたのです。
一人一人の生きている意味と尊厳の重みを社会の営みごと奪い去るという、非人道性の極みに対する戸田会長の憤りを、不二の弟子として五体に刻みつけたことを、昨日の出来事のように思い起こします。
私自身、1983年以来、「SGIの日」に寄せた提言を40回にわたって続ける中で、核問題を一貫して取り上げ、核兵器禁止条約の実現をあらゆる角度から後押ししてきたのも、核問題という“現代文明の一凶”を解決することなくして、人類の宿命転換は果たせないと確信してきたからでした。
時を経て今、戸田会長の「原水爆禁止宣言」の精神とも響き合う、核兵器禁止条約が発効し、第1回締約国会合がついに開催されるまでに至りました。
広島と長崎の被爆者や、核実験と核開発に伴う世界のヒバクシャをはじめ、多くの民衆が切実に求める核兵器の廃絶に向けて、いよいよこれからが正念場となります。
私どもは、その挑戦を完結させることが、未来への責任を果たす道であるとの信念に立って、青年を中心に市民社会の連帯を広げながら、誰もが平和的に生きる権利を享受できる「平和の文化」の建設を目指し、どこまでも前進を続けていく決意です。
* * * * *
注6 新戦略兵器削減条約(新START)
第1次戦略兵器削減条約(START1)の後継となる条約として、2011年2月に発効したアメリカとロシアの核軍縮条約。条約の期限が迫った昨年2月、2026年まで条約の期限を延長することが決まった。中距離核戦力全廃条約の失効に続いて、領空開放(オープンスカイ)条約からも米ロ両国が離脱する中、核兵器を巡る状況が不安定さを増すことが懸念されている。
|