|

1997年7月に行われた第13回本部幹部会でスピーチする池田先生(八王子市の東京牧口記念会館で)
日蓮大聖人は仰せである。
「寂光の都ならずは何くも皆苦なるべし本覚の栖を離れて何事か楽みなるべき、願くは『現世安穏・後生善処』の妙法を持つのみこそ只今生の名聞・後世の弄引なるべけれ須く心を一にして南無妙法蓮華経と我も唱へ他をも勧んのみこそ今生人界の思出なるべき」(全467・新519)
――「寂光の都」以外は、どこも皆、苦しみの世界である。(永遠の生命を自覚した)真実の覚りの住みかを離れて、何が楽しみであろうか。否、何もない。願わくは「現世は安穏であり、来世は善いところに生まれる」力をもつ妙法を持ちなさい。それだけが、今世には真の名誉となり、来世にも真の幸福へと導いてくれるのである。どこまでも一心に、南無妙法蓮華経と自分も唱え、人にも勧めていきなさい。まさにそれだけが、人間界に生まれてきた今世の思い出となるのである――。
「本当の楽しみは広宣流布の活動にしかない。自行化他の行動のなかにしかない」との仰せなのである。
大聖人は、法華経は「不老不死」の大法であると仰せである。
「老い」にも苦しまない。「死」にも苦しまない。信心の炎があるかぎり、永遠に生命力の火は燃え続ける。生死を超えた大確信で生きていける。一生涯、希望を燃やして、生きぬいていく。その原動力のエンジンが信心である。
長寿社会――その模範が学会なのである。これ以上の人生の軌道はない。
人のつながりが境涯を広げる
「境涯を広げる」には、どうすればいいか。それには「人間関係を広げる」ことである。ゆえに、幹部一人一人は「人間と結合する」ことである。会員とつながり、人間とつながってこそ本当の幹部である。
大事なのは「人間と人間のつながり」である。「人間と人間の打ち合い」である。内外の多くの人々と結び合い、つき合っていくことである。その人は、その分だけ生命が広がる。豊かな人生になる。
トルストイは、臨終の間際に、かわいがっていた末の娘をそばに呼び、遺言を伝えた。
その要点の一つは「生命は他の生命と多く結びつくほど、自我が拡大する」ということであった。これを忘れてはいけないと言い残したのである。
私どもで言えば、対話であり、弘教であり、広宣流布である。
ゲーテは言う。
「他人を自分に同調させようなどと望むのは、そもそも馬鹿げた話だよ」「性に合わない人たちとつきあってこそ、うまくやって行くために自制しなければならないし、それを通して、われわれの心の中にあるいろいろちがった側面が刺激されて、発展し完成するのであって、やがて、誰とぶつかってもびくともしないようになるわけだ」(エッカーマン『ゲーテとの対話』山下肇訳、岩波文庫)
一人でも多くの人と語った人が勝利者である。人の面倒をみてあげた分だけ、勝利である。いろんな人々と、がっちりギアをかみ合わせて、広宣流布へと向かわせてあげた分だけ、自分が勝つ。
牧口先生の広布の宣言
初代会長牧口先生以来、創価学会の目的は「広宣流布」である。
では、牧口先生が「広宣流布」という言葉を公式の場で初めて使ったのは、いつか。いつ、「創価学会は広宣流布を目指す団体である」ことを宣言なされたのか。それは決して、学会が順風の時ではなかった。それどころか、弾圧のさなかであった。
昭和17年(1942年)5月。創価教育学会の第4回総会が開かれた。
太平洋戦争の開戦から、半年余りたっていた。
初めのうち、日本は連戦連勝だった。しかし、続くわけがない。すぐに行き詰まった。転落が始まった。それなのに、国民には“ウソ八百”の情報しか流されなかった。だから、本当のことがわからず、「すごい日本だ」「神国日本だ」と、国中が戦勝気分に酔っていた。
しかし、すでにその時、牧口先生は「日本は滅亡する。絶対に滅びる」と、鋭く見ぬいておられた。法眼というか、仏眼というか、透徹した信心と人格の明鏡があった。
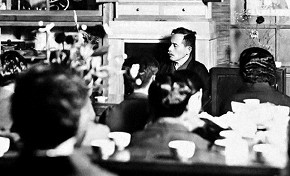
1942年、都内で行われた座談会に出席する牧口先生。軍部政府の弾圧が強くなる中、牧口先生は仏法の正義を訴えた
総会で、先生は訴えた。「我々は国家を大善に導かねばならない。敵前上陸も同じである」(『牧口常三郎全集』第10巻。以下、引用は同書から)
わからずやの悪人ばかりのなかに入って大善を教えるのは、“敵の目前に上陸する”のと同じであるというのである。
そして先生は叫ばれた。
われわれは「家庭を救ひ社会を救ひ、さうして広宣流布に到るまでの御奉公の一端も出来ると信ずるのであります」
これが、「広宣流布」の初めての公式発言であった。「広宣流布に到るまで」わが身をささげきっていくのだとの宣言である。
大変な時こそ一番厳しい所へ
事実、牧口先生は、「広宣流布」へと前進した。迫害のなか、240回を超える座談会を開催(昭和16年5月から同18年6月まで)。あのお年で、240回である。(同18年当時、72歳)
また、地方にも単身、出かけられた。みずから約500人の人々を信仰に導いたといわれている。(同5年から逮捕される18年7月まで)
いちばん「大変な時」に、「大変な所」から始める。ここに偉大な歴史が開かれる。本当の歴史が始まる。この学会精神を深くかみしめていくべきである。
戸田先生も、戦後のいちばん大変な時に「今こそ広宣流布の時だ」と立ち上がった。状況が厳しければ、その時にこそ、勇気を奮い起こすべきである。
日蓮大聖人は仰せである。
「悪王の正法を破るに邪法の僧等が方人をなして智者を失はん時は師子王の如くなる心をもてる者必ず仏になるべし」(全957・新1286)
――悪王が正法を破ろうとして、邪法の僧らが悪王に味方し、智者を滅ぼそうとする時、師子王のごとき心をもつものが、必ず仏になることができる――。
臆病者は、仏になれない。「師子王の心」をもたなければ、仏になれない。厳しければ厳しいほど勇み立つ。
ここに、学会精神の真髄がある。いちばん大変な所に、みずから足を運んでこそ、「道」は開かれる。
人材革命の波を わが地から!
牧口先生が「広宣流布」を叫んだころ、宗門は何をしていたか。「広宣流布」を破壊しようとしていた。昔も今も変わらない。
当時、宗門は御書の発刊を禁止し、「日蓮は一閻浮提第一の聖人なり」(全974・新1315)の御文をはじめ、大切な14カ所の御聖訓を削り取った。
さらに宗門は、大石寺に「神札」をまつり、牧口先生にも「神札を受けよ」と迫った。なんという大謗法か。しかも牧口先生が「絶対に受けません」と断ると、陰で学会の弾圧に味方したのである。
一方、牧口先生の弟子たちは、どうだったか。
皆、牧口先生の勢いに驚き、おびえた。皆、獅子ではなく、猫や鼠だったのである。
「広宣流布」「国家諌暁」――こう牧口先生は叫ぶ。それに対して弟子たちは、「今の時期に無茶だ」「時期尚早だ」「皆、憲兵隊に連れて行かれてしまう」と、おびえた。
こういうなか、戸田先生だけが「ぼくは牧口先生の弟子だ」「あくまで、ぼくは牧口先生にお供するよ」と、淡々としておられた。厳かな師弟の姿である。
そして戸田先生は「あなたの慈悲の広大無辺は、わたくしを牢獄まで連れていってくださいました」と師匠に感謝をささげたのである。牢獄につながれて、文句を言うどころか、戸田先生は感謝すらされている。一緒に難を受けさせていただいた、なんとありがたいことか、と。これが「師弟」である。
そして戸田先生は生きて出獄し、師匠が掲げた「広宣流布」の旗を、ふたたび厳然と掲げて、一人立った。師弟は一体不二であったゆえに、恩師の死を乗り越えて、「広宣流布」のうねりは広がっていったのである。この「師弟不二の道」を、永遠に忘れてはならない。

学会創立100周年へ新たな前進を誓う第11回本部幹部会。席上、VOD新番組「新しき人材で広宣流布の前進を!」が上映された(今月12日、巣鴨の東京戸田記念講堂で)
広宣流布の法戦にあっても、リーダーが前進すれば、皆が前進する。リーダーが伸びれば、皆が伸びる。リーダーが口先だけでは勝てるわけがない。
「自分が人間革命していこう!」「自分を鍛えていこう!」――こう決意して、まず自分が行動していくところに、常勝の原動力が生まれる。これ以外に常勝の方程式はない。
御聖訓に云く「法自ら弘まらず人・法を弘むる故に人法ともに尊し」(全856・新2200)――法は、ひとりでに弘まるのではない。人が法を弘めるのであり、だからこそ弘める人も弘まる法も、ともに尊い――と。
広宣流布は、すべて「人材」で決まる。新しき人材を見つけ、新しき人材を育て、新しき人材を結集していく。その人が人材である。この「人材革命」の波を、21世紀へ、もう一度、創価学会はつくりあげていきたい。
こう申し上げ、本日の私のスピーチを終わります。長時間、ありがとう!
|