| Ⅱ部 第19回 2020年08月18日 「大衆とともに」――公明党の結党③ |
| 〈出席者〉西方男子部長、大串女子部長、樺澤学生部長、林女子学生部長 1961年 公明政治連盟(公明党の前身)を結成 政界の浄化、国民の幸福のために ◆西方 学会は、宗教者の社会的使命として政治に関わり、支援活動をしてきました。 そして1961年(昭和36年)11月に、公明党の前身である公明政治連盟(公政連)が結成されます。 小説『新・人間革命』第5巻「獅子」の章には、「『公明政治連盟』という政治団体結成に踏み切った最大の理由は、創価学会は、どこまでも宗教団体であり、その宗教団体が、直接、政治そのものに関与することは、将来的に見て、避けた方がよいという判断からであった。いわば、学会として自主的に、組織のうえで宗教と政治の分離を図っていこうとしていたのである」と記されています。 ◇原田 本来、宗教団体が政治に関与することは憲法で保障された自由であり、権利です。 日本国憲法第20条には、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」とあり、これに続いて、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」とうたわれています。 これは、「信教の自由」を確保するため、国や国家の機関が、その権力を行使して宗教に介入したり、関与することがないよう、国家と宗教の分離を制度として保障したものです。 一方、宗教団体が選挙の折に候補者を推薦したり、選挙の支援活動を行うことも、結社や表現、政治活動の自由として、憲法で保障されています。 また、そうして推された議員が、閣僚等の政府の公職に就くことも認められています。 このことは、国会でも、内閣の「憲法の番人」といわれる歴代の内閣法制局長官が、何度も明言しています。 「憲法の定める政教分離の原則と申しますのは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨である」「宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」と。 ◆樺澤 憲法学者の竹内重年氏も、「日本国憲法の精神が求める政教分離は、国家の宗教的中立性を要求しているのであって、宗教者の政治的中立を要求しているわけではありません」と明快に述べています。 ◇原田 憲法にうたわれた「政教分離」の原則とは、戦前、戦中の、国家神道を国策とした政府による宗教弾圧の歴史の反省の上に立って、欧米の歴史を踏まえつつ、「信教の自由」を実質的に保障しようとするものにほかなりません。 明治憲法では、その第28条で「信教の自由」を規定していましたが、政府は、神社神道を国家の祭祀とすべきものであり、“宗教に非ず”として、国家の特別な保護下に置いていったのです。そして、事実上、国家宗教に仕立て上げられていきました。 軍部政府は、この国家神道を精神の支柱として戦争を遂行するため、その考えに従わない宗教を容赦なく弾圧していきました。その中で創価学会への大弾圧も起こったのです。 神札を祭らぬことなどから、「不敬罪」「治安維持法違反」に問われ、牧口先生、戸田先生は、投獄されました。しかし、牧口先生も戸田先生も、「信教の自由」を守るために戦い抜かれました。そして、牧口先生は獄死されたのです。学会にとって、忘れてはならない歴史です。 ◆樺澤 世界74カ国・地域に広がるカトリックの信徒団体で、事務総長を務めるクァットルッチ氏は語っています。 「政治家の良心を保つための薬こそ、『宗教』であると断言したい」「日本では、いまだに、“宗教家は政治に口出しするな”ということを言う人がいるようですが、それは、国家の成長を妨げる浅薄な言論です。宗教的思想を根本に、自らを律し、正義の信念に生きる者こそ、より積極的に政治に関わるべきです」「その意味においても、学会には、一層、政治に積極的に関わっていただきたい」と。 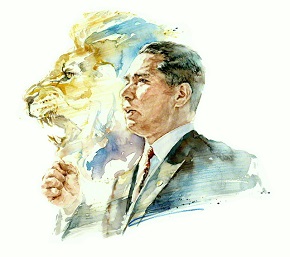 広布とは「獅子の道」である。何ものをも恐れぬ「勇気と正義と信念の人」でなければ、広布の峰を登攀することはできない 民衆から信頼と支持を得る団体 ◆西方 歴史を振り返れば、学会が初めて関わった、55年4月の統一地方選の際、候補となった人たちは、当時の保守政党や無所属、野党など、さまざまな政党から出馬しています。 ◇原田 戸田先生には党派へのこだわりはなく、一人一人の議員が好きな政党に所属して活動すればよいと言われていました。それぞれの立場で、政界の浄化のために立ち上がり、政治を民衆の手に取り戻すことを念願されていたのです。 しかし、実際に議員活動を開始してみると、どの政党の在り方にも、議員たちは心から賛同することはできませんでした。そこで、政治団体の結成を考えるようになったのです。 そして、61年11月に公政連が結成されます。その際、池田先生は明確に言われています。 「この政治団体は、学会のためのものではない。私は、そんな小さな考えではなく、広く国民の幸福を願い、民衆に奉仕していく、慈悲の精神に貫かれた新たな政治団体をつくろうとしているのです」「私の願いは、政治団体がスタートしたならば、一日も早く自立し、民衆の大きな信頼と支持を得るものにしていってほしいということです」「学会は、その母体として今後も選挙の支援はしていきます。しかし、具体的な政策については、皆でよく話し合い、すべて決定していくのです」と。 だからこそ、公明党の議員は、国民のため、社会のため、命懸けで働いてもらいたい。  公明党の公害追放全国大会で、イタイイタイ病の実情を訴える患者を支える公明議員(1970年9月、都内で) 時代を変革する女性の生活感覚 ◆林 「公明」との名称に至った経緯についても、「獅子」の章に描かれています。 ◇原田 戸田先生は56年7月の初めての参院選の直後、当選したメンバーに、「君たちは、どの政党に入ってもよいが、もし、将来、君たちが会派をつくろうという時には、“公明会”としよう」「学会の選挙運動は、金もかけず、買収などとは無縁の公明選挙であるし、宴会政治のような腐敗した政界を正すのが君たちの使命であるからだ」と言われたそうです。 「公明」という名称には、清潔な政治の実現を願われた戸田先生の思いが込められているのです。こうした戸田先生とのやり取りを、池田先生から教えていただいたことがあります。 ◆大串 その後、64年11月に公明党が結党され、都議会議長選を巡る汚職事件で都議の逮捕が相次いだ「都議会リコール解散の主導」や「宴会政治追放」をはじめ、「イタイイタイ病の『公害病』認定」「政党で初の全国『公害総点検』」「“隅田川し尿不法投棄”の摘発」などを実現していきます。 ◇原田 公害問題について、作家の有吉佐和子氏は、ベストセラー『複合汚染』の中で、「この問題を国会で取り上げ政府の無為無策をきびしく追及したのは(67年5月の)公明党だった」とつづっています。 また、池田先生と対談集『地球革命への挑戦――人間と環境を語る』を編んだ、世界的な環境学者であるドイツのヴァイツゼッカー博士は、「一九七〇年代のドイツは、環境問題に関しては間違いなく日本から学ぶ立場にありました。日本に水俣病やイタイイタイ病が発生したのは、一九五〇、六〇年代のことでしたね。それによって、日本は他の諸国に先駆けて、重金属と大気環境についてのきわめて厳しい基準を設けました」と語っていました。この問題で、公明党が果たした役割は実に大きかったのです。 ◆大串 『新・人間革命』第6巻「波浪」の章に「選挙の支援活動の、大きな推進力となっていたのが、一般的には政治への関心が低いといわれていた主婦層にあたる、婦人部員であった。それは、政治を自分たちの手に取り戻そうとする、目覚めた大衆の、新しい力の台頭であった」と書かれています。現在にも通じる、学会婦人部の姿であると思います。 ◇原田 思えば、日本で初めて、女性の参政権が行使されたのは、46年4月10日の衆院選です。それまでの長きにわたる女性運動が、ようやく戦後の連合国軍指揮下の民主化によって、報われたのです。 現実を鋭く捉える女性の生活感覚。生命を育む側からの発想。平和のため、次世代へとつなげるための未来への選択。こうした女性の声が、時代を変えてきました。 生命尊厳の哲理を掲げた、学会婦人部の使命は、ますます大きくなっているのです。 米エマソン協会のサーラ・ワイダー元会長は、「人と人を結びつけ、多くの人々に励ましを贈り続けておられる創価学会の婦人部の皆さんは、本当に素晴らしいです」「私は、創価学会の女性たちに無限の希望を抱いております。とりわけ、女性たちの助け合い、励まし合いに満ちた姿は印象的です」と語っています。 婦人部の皆さんの行動は世界の知性が高く評価する、社会変革の運動なのです。  2009年11月、信濃町の創価世界女性会館を訪れた米エマソン協会元会長のサーラ・ワイダー博士を、創価の女性が歓迎 |