| Ⅱ部 第14回 2020年07月20日 御書根本を貫く民衆仏法の学会教学③ |
| 〈出席者〉西方男子部長、大串女子部長、樺澤学生部長、林女子学生部長 青年の育成が未来を創る ◆西方 顕仏未来記に「伝持の人」(御書508ページ)とあります。池田先生は、「『伝持の人』とは『後継の人』ともいってよい」「未来部の前進が、広布の前進だ」と、未来を担う各部の育成に全力で取り組まれてきました。 ◇原田 先生が高等部を結成されたのは、1964年(昭和39年)6月です。第3代会長就任後、最初につくられた部となり、その翌年に中等部、少年少女部(当初は少年部)の結成へと続いていきます。 当時の学会の幹部には、そうした発想は全くなく、「未来のための布石は大切ですが、優先すべきことが、たくさんあるように思います」と言う幹部もいました。 しかし、先生は断言されたのです。「三十年後、四十年後の学会をどうするのか。その時、学会の中核になっているのが、今の高校生です。苗を植えなければ、木は育たない。大樹が必要な時になって苗を植えても、手遅れだ」と。 先生は常に、広宣流布の未来を見据えておられました。また当時、社会では少年の非行が深刻化し、青年の目的観の欠如が叫ばれていた時代でした。 高等部の誕生は、こうした時代の状況に希望の灯をともすものでもあったのです。 “皆が大指導者に! 全員が広布の大闘将に!” ◆樺澤 66年1月からは、先生が毎月、高等部の代表に直接、御書講義をされています。 ◇原田 その前年に先生は「大白蓮華」11月号に巻頭言「鳳雛よ未来に羽ばたけ」を発表され、高等部に「勉学第一」の指針を贈られました。 そして翌66年、「黎明の年」とともに「高等部の年」と銘打たれたこの年の1月から、男女高等部の代表への御書講義を開始してくださったのです。 教材は「諸法実相抄」「生死一大事血脈抄」「佐渡御書」などの重書でした。難解な御文もありましたが、受講生は皆、懸命に予習を重ね、司会が拝読を求めると、先を争うように全員の手が挙がったといいます。先生は、当時の真情を随筆にこうつづられています。 「寸暇を惜しんで重ねた一回一回の講義は、『今しかない、今しかない』と必死だった。『皆が大指導者に! 全員が広布の大闘将に!』と祈り、叫ぶ思いであった。だから私は、“まだ子どもだから”と、甘やかすことはしなかった。真の弟子を育てようと本気になれば、自ずと指導にも力が入った」と。  高等部の代表に対する池田先生の第1回御書講義。6月の第1期の修了式まで、渾身の講義は毎月、行われた(1966年1月、東京・信濃町の学会本部で) ◆林 先生の未来部への万感の思いが伝わってきます。同年6月の1期生の講義修了時には、受講メンバーで「鳳雛会」(男子)、「鳳雛グループ」(女子)が結成されました。 ◇原田 私は先生の高等部員に対する信頼を、まざまざと目にした思い出があります。 それは66年7月16日、当時の箱根研修所で「鳳雛会」「鳳雛グループ」1期生が、先生のもとに集って行われた第1回野外研修でのことです。私は聖教新聞の記者として、取材でその場に同席していました。 衝撃でした。先生は高校生に対して、一個の人格として接しておられたのです。 自身の宿命に悩み、涙ながらに相談したメンバーに、「信心は感傷ではない。泣いたからといって、何も解決しないではないか!」と厳しく言われ、勝つための人生を開く正しい信心の在り方を、厳愛をもってご指導される場面もありました。 私は正直、子どもたちに“受け止められるだろうか”と思うこともありました。しかし、それは、いらぬ心配でした。 先生はメンバーに語られました。「私は、今日集まった諸君を、頼りにしてまいります。諸君が成長してくれれば、私も、年ごとに安心することができる」「諸君は、私と師弟の絆で結ばれた人であると思っているが、そう信じていいですね」 「はい!」――その響きには真実がありました。ここに「師弟」がある。ゆえに「信頼」があり「訓練」がある。私は高等部の皆さんから教えていただいた思いでした。 鳳雛会は、その後も期を重ねるとともに、北は北海道から南は沖縄まで、各方面に結成され、68年10月には、定時制にも鳳雛会がつくられました。 鳳雛会のメンバーは、やがて、学会の最前線で、また社会の中核で活躍していくことになります。 一日に30分でも5ページでも拝読を ◆大串 先生は女子部に対しても、幾度となく教学の大切さや、御書根本の生き方を教えてくださっています。 ◇原田 かつてある女子部幹部が、先生に女子部の人材グループ「青春会」の人選基準について尋ねた際、こうご指導されました。 「教学の力のある人を選ぼう。戸田先生は『女子部は教学で立て』と言われたが、それは人生の哲学を確立しなさいということだ。教学という生き方の哲学がなければ、仏法のうえからの重要な指導を、受け止めていくことはできないからね」 そうして結成された「青春会」のメンバーにも先生は、「人生の確かな哲学の骨格をつくる意味から、まず、御書を読破していくようにしたい。難解な箇所もあるかもしれないが、御書をすべて拝しておけば、それが一つの自信にもなる。したがって、一日に三十分でも、あるいは、五ページぐらいでもいいから、着実に学んでいっていただきたい」と具体的に示されたことがありました。 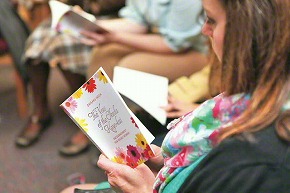 世界同時進行で、女子部が「池田華陽会御書30編」の研さんに励む ◆林 女子部は今、その伝統を受け継ぎ、「池田華陽会御書30編」の読了運動に取り組んでいます。また、世界の多くの国々でも、女子部員が御書30編を同時進行で学んでいます。 ◇原田 とても素晴らしいことです。御書30編には、五大部をはじめ、女性門下に宛てられた御消息文などもあります。青春時代に何度も繰り返し拝して、その一節一節を行動に移していくことが大事です。 女子部の皆さんが、御書根本に「実践の教学」に励む姿は、「女子は門をひらく」(同1566ページ)との日蓮大聖人の仰せ通り、広宣流布の未来を開くことにつながるのです。 「翻訳事業」は万年に残る大聖業 ◆樺澤 先生は66年から、未来への布石として御書の英訳を推進されます。また68年8月には、学生部の代表で翻訳・通訳メンバーの「近代羅什グループ」(男子)、「近代語学グループ」(女子)を結成されました。 ◇原田 大聖人の御精神を世界へ広げていく上で、御書の各国語への翻訳は不可欠です。また先生ご自身が世界の超一級の識者と対談される中、人一倍、世界に通用する語学力と人間力を身に付けた人材を必要とし、求められていたのです。 71年には国際部が結成され、語学力を兼ね備えた人材の裾野は、さらに広がっていきました。そして、御書の英訳作業は着実に進み、99年(平成11年)に世界の同志が待望した『英訳御書』上巻が発刊されました。  翻訳家のバートン・ワトソン博士㊨、リチャード・ゲージ氏㊥と語り合う池田先生。ゲージ氏は小説『人間革命』や、トインビー博士ら多くの識者との対談集を英訳してきた(2005年5月、創価大学で) ◆西方 その翻訳の監修を務めたのが、中国語・日本語の高名な翻訳家である米コロンビア大学のバートン・ワトソン博士です。 ◇原田 博士は、司馬遷の『史記』を初めて英訳した中国文学研究の第一人者であり、これまで全米翻訳賞や世界ペンクラブ翻訳賞、文学アカデミー賞などを受賞しています。 池田先生と博士は、73年12月以来、6度会見をされました。これまで、鳩摩羅什訳『法華経』、『英文御書選集』『御義口伝』をはじめ、先生の著作なども英訳され、仏教の真髄を世界に伝える労作業に力を注いでこられました。 ◆大串 2006年には、『英訳御書』下巻が発刊され、御書全集のほぼ全編が翻訳・出版されています。 ◇原田 英訳の完結によって、欧州各国語や南米諸言語への御書翻訳が大きく前進し、世界への広宣流布は一段と加速することになりました。 本年5月3日には、池田先生の50言語目の著作となるスペインのガリシア語、バスク語版の『一生成仏抄講義』が発刊されています。御書の翻訳事業は、万年の未来に残る不滅の大聖業として、仏法史に燦然と輝き渡っているのです。 明年11月18日に新版御書を発刊 ◆西方 振り返ると、英語版機関誌「セイキョウ・タイムズ」に初めて英文の御書が掲載されたのが、半世紀以上前の1966年です。当時は、誰も今日のことを想像もできなかったと思います。 ◇原田 先生がただお一人、世界広布のために手を打ち、語学ができる人材を育成され、道を開いてこられたからこそ、今日の世界宗教としての大発展があります。 明2021年11月18日には、日蓮大聖人御聖誕800年を慶祝して、新版の御書全集が発刊されます。 池田先生の監修のもと、文字を大きくし、会話文には、かぎかっこを加えるなど、より読みやすくなるよう工夫を凝らすとともに、現在の御書全集が発刊された後などに発見された真筆の御書も収録する予定です。 民衆に開かれた人間主義の仏法を、共々に学び深め、行学錬磨の仏道修行に、一層、まい進していきたいと思います。 |