|
〈出席者〉西方男子部長、大串女子部長、樺澤学生部長、林女子学生部長
東奔西走の激務の中「人間革命」を連載
“ただ会員のため”の命懸けの執筆
◆大串 今、世界中で、青年が小説『人間革命』『新・人間革命』を学び、信心を深め、活動の糧としています。原田会長は『人間革命』の初代編集担当者として、池田先生の執筆闘争を間近で見てこられました。特に、どのような点が心に残っていますか。
◇原田 『人間革命』には、学会精神の正史、三代の師弟の魂、民衆運動の軌跡がつづられています。それは、広布に進む同志の原動力になるとともに、はるか未来の人々のために書かれたものでもあると思います。
私は、第1巻から第3巻まで、担当させていただきました。連載開始の1965年(昭和40年)当時は、大学を卒業して、聖教新聞社の新入職員として働き始めて1年目でした。先生は、前年12月2日に沖縄の地で執筆を開始され、約2週間後には13回分の原稿をくださいました。
当時の新聞制作は活版印刷です。今の人たちには想像もつかないかもしれませんが、原稿をもとに、職人が一つ一つ鉛の活字を拾い、版を作っていく。できるだけ早く作業をするために、原稿をはさみで切り分けて数人で分担する。つまり、元の原稿は後に残らないわけです。
当時は、コンピューターはおろか、今のようなコピー機も普及していません。“先生の原稿を歴史に残さなければならない”との思いで、私自身が“人間コピー機”になって自分の手で書き写した原稿を工場に届け、直筆の原稿は保管していきました。
原稿が届き、すぐさま書き写し始めたところ、1回分の書写が終わる前に、次回分、さらに次々回分と、先生からものすごい勢いで原稿が届いたことが何度もありました。その気迫、スピードのすさまじさに圧倒される日々でした。
当初、聖教新聞は週3回発行でしたが、同年の7月15日付から日刊になり、小説の連載も週3回から倍以上になりました。先生は、東奔西走の激務の中での執筆であり、まとめて頂戴していた原稿もあっという間に少なくなっていきます。
いよいよ、原稿がなくなってしまった日、私は「先生、今夜いっぱい、まだ時間がありますから、明日の降版分を、よろしくお願いします」と、なるべくご負担をお掛けしないように、言葉を選んで申し上げました。すると先生は「うん、分かったよ」と答えられ、一気に書き進めてくださったのです。切羽詰まった様子の私のことを心配してくださったのだと思います。
後年、先生は、随筆に「彼(担当者‖編集部注)のために、苦しませてはならぬと、しぜんに無理をして書く」と、その時の心境をつづってくださいました。
また当時、私は独身寮で生活していました。ある時、ゲラ刷りを届けに学会本部の先生のもとへうかがい、社に戻りました。その直後、先生から「靴下」が届いたのです。私の靴下に穴があいているのを、ご覧になった先生のご配慮でした。激闘の渦中にあっても、新入職員の身だしなみにまで心を砕いてくださり、感激で胸がいっぱいになったことを、今も鮮明に思い出します。
地方指導に行かれる際も、海外への平和旅の際も、先生はいつも原稿用紙の入ったかばんをお持ちでした。分刻みのスケジュールを終え、宿舎に戻ってからも、先生は深夜まで執筆を続けておられました。
担当者として、先生のご執筆の様子を目の当たりにする中で、日刊紙に小説を連載するのがどれほど大変なことなのかを、肌で感じました。そして、その命懸けの執筆闘争を支えていたのは「師匠の偉業を宣揚する」との、弟子としての誓願であったのです。
そのことを痛切に感じたのは、後に『人間革命』が映画化された際のことです。東京・江戸川区にあった撮影のロケ地を訪問された先生は、帰りの車中でこう語られました。
「牧口先生、戸田先生を宣揚するとはいっても、また、牧口門下がいかに多しといえども、牧口先生、戸田先生を現実に宣揚しているのは、誰もいないじゃないか! だから、私は、先師、恩師の偉業を書き残さなければならない。それが弟子の道じゃないか!」と。師弟の真髄を教えていただき、命が震えました。
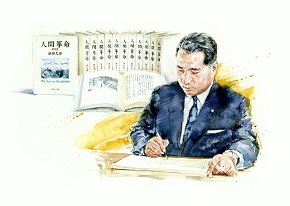
「戦争ほど、残酷なものはない」――1964年12月、池田先生は小説『人間革命』の執筆を開始した(イラスト・間瀬健治)
「世界中の人に」戸田先生の熱願
◆林 先生の、聖教新聞に対する思いについても、お聞かせください。
◇原田 そもそも、聖教新聞の発刊の原点は、50年8月24日、事業が行き詰まり、苦境に立たされていた時、戸田先生が池田先生に、こう語られたことにあります。
「一つの新聞をもっているということは、実に、すごい力をもつことだ。学会も、いつか、なるべく早い時期に新聞をもたなければいけない」と。
この師弟の語らいから出発し、翌51年4月20日に創刊されました。その直後の5月3日には戸田先生が第2代会長に就任。以来、今日に至るまで聖教新聞は広布推進の原動力となってきたのです。この間、池田先生は、自ら原稿を書かれ、見出しやレイアウト等にも細やかなアドバイスをされ、そして、誰よりも配達員の無事故を祈り抜いてくださいました。
昨年、世界聖教会館が完成した時、私の胸に真っ先にこみ上げてきたのが、聖教新聞をここまで大きく育ててくださった先生への尽きせぬ感謝でした。
今や、世界50カ国・地域で80以上の姉妹紙・誌が発行され、聖教電子版には、203カ国・地域からアクセスがあります。聖教新聞を「日本中、世界中の人に読ませたい」という戸田先生の熱願を、池田先生は現実のものにされたのです。

東京・信濃町に立つ「創価学会 世界聖教会館」は、創価の人間主義の哲学と、励ましの言葉を世界へ発信する、民衆凱歌の言論城
体調不良の時は録音機使い口述
◆樺澤 『人間革命』『新・人間革命』を、より深く研さんしていくために、大切なことはありますか。
◇原田 執筆当時の歴史を学んでいくことも大事です。時代背景を知ることで、小説を通し、同志を鼓舞しようとされている先生のお心が伝わってきます。
たとえば、『人間革命』第6巻「七百年祭」の連載が開始されたのは70年2月です。その前年12月の関西指導の前から、先生は体調を崩され、高熱を押して指導旅を敢行されました。年が明けても体調不良が続くなか、前年8月から休載していた『人間革命』を再開されたのです。
◆西方 69年末から70年初めといえば、あの言論問題が起こり、誹謗・中傷の嵐が学会を襲っていた時です。
◇原田 そうです。当時、池田先生の執務室にオープンリール式のテープレコーダーが運び込まれました。大きく、重い機械です。体調が優れぬ先生は、その機械を使って口述されました。実際に、先生が吹き込んだテープには、口述しながら咳き込む声、水を飲む音、荒くなった呼吸などが、そのまま録音されています。
なぜ、先生はそこまでして執筆されたのか。言論問題は、先生の会長就任以来、学会が直面した最大の試練でした。
実は、この背景には、64年に結党された公明党が平和と福祉の党として発展を遂げ、69年末の衆院選では改選前の約2倍に当たる47議席を獲得。第3党に躍り出たということがありました。公明党の躍進に危機感をもった一部の政党は、70年に入ると、学会が言論弾圧したとして、国会の場で狂ったように攻撃を開始しました。一部のマスコミも、それに同調する報道をしていました。
学会の対応に未熟な部分があったことは事実ですが、事の本質は、新たな民衆勢力の台頭を阻もうとした既成の勢力による宗教弾圧でした。
この時も、先生は一人、屋根となって、辛労を尽くされ、学会を守り、会員を守りながら、新しい広布の道を切り開いてくださったのです。今、当時のことを思い起こすたびに、報恩の心を新たにいたします。
こんなこともありました。ある時、先生は箱根の研修所(現・神奈川研修道場)で、夜遅くまで会員の指導を続けられていましたが、いくつかの卑劣な学会攻撃の報告を聞かれると、直ちに「本部に戻る」と決断されたのです。
発熱など、連日の体調不良に苦しまれていた時期です。冬場でもあり、先生のお体を気遣って、止める声もありました。しかし、先生は深夜、同所を出発、未明に本部に戻られ、そのまま、首脳の皆さんと、いかに同志を守り、事態を開いていくか、協議を重ねられたのです。
そして、先生は、こう叫ばれました。「私は戸田先生の弟子である。何を言われようと、何があっても平気だ。恐れるものなど何もない!」
まさに師子吼でした。
その一方で、一人一人の会員のことを深く憂慮してくださり、「多くの純真な学会員に、悲しい思いをさせるのは可哀想だ」「ご主人が未入会の婦人が、どんなに辛い思いをするか」と、それはそれは心を砕いておられました。
このような状況の中で、『人間革命』第6巻「七百年祭」の連載が、2月9日から始まったのです。当初、連載開始は「2月11日」を予定していました。当時の聖教には、「一日も早く再開してほしいとの全国の読者の強い要望等もあり」掲載が早まったとあります。さらに、土、日曜日は休載の予定だったのが、読者からの要望に応えて、日曜のみの休載になったことも報じられています。
この章には、戦後、戸田先生のもとで池田先生をはじめとした当時の青年部が、宗門の邪悪と戦った歴史がつづられています。理不尽な迫害とは断じて戦うとの正義の闘争が描かれている章でした。
先生は、ご自身が最も大変な中にあっても、ただただ会員のために、まさに命懸けで執筆を続けてこられました。池田先生の言論闘争とは「会員を守り抜く」「会員を励まし抜く」という信念に基づくものであったのです。
こうした大激闘の中、この70年の9月28日に聖教新聞の本社ビル(旧本社)が落成しました。昨年、先生が世界聖教会館を初訪問してくださったのは、それから49年後の同じ日です。
先生の真心に、感謝の念は尽きません。私たちは、師匠の大恩に応えるために、友を幸福へ、世界を平和へ導く正義の言論戦を貫いてまいりたい。
|